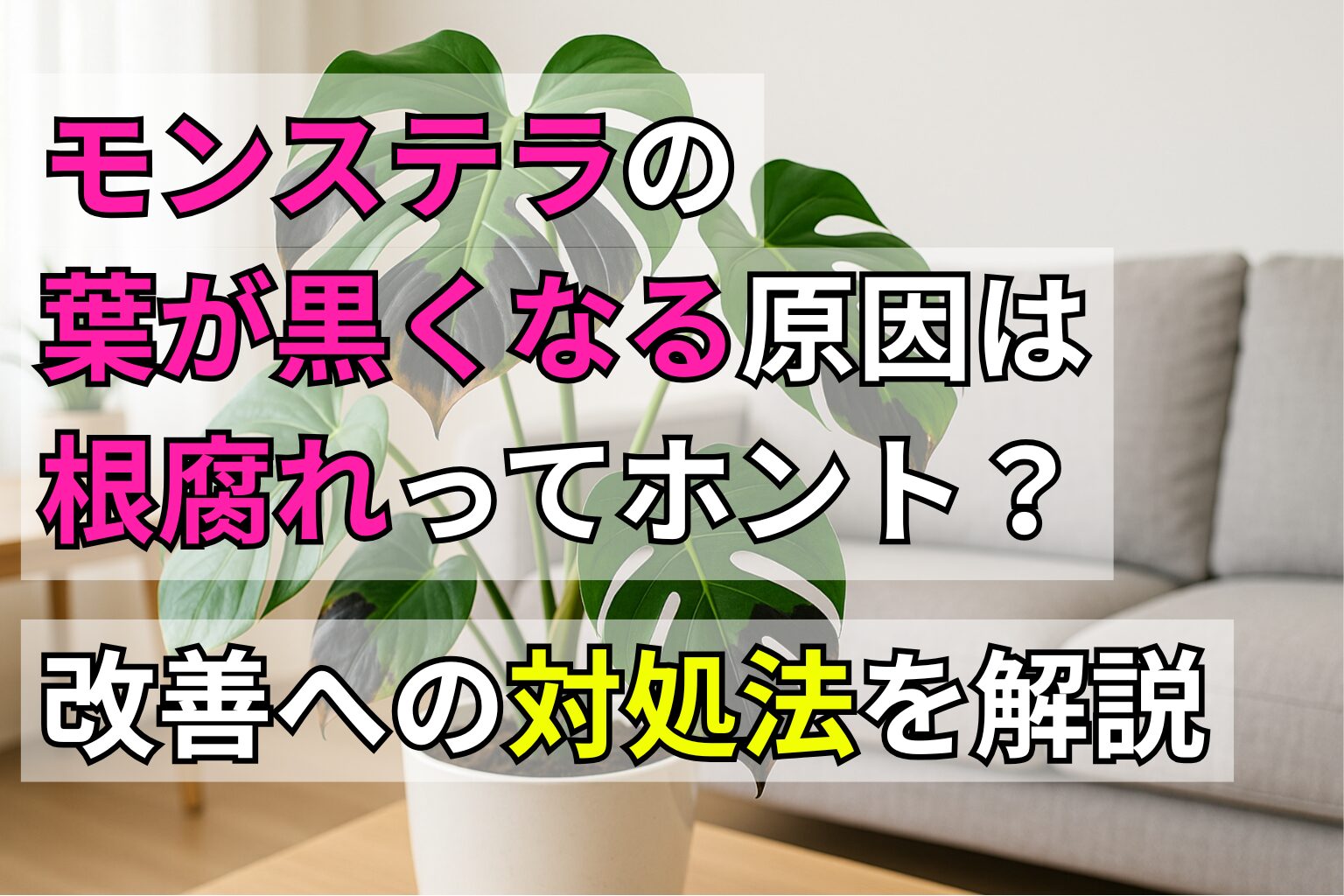日頃から大切に育てているモンステラ。そのモンステラの葉が黒くなる姿を見て、「なにか異変が起きているんじゃないか」と心配になりますよね。実はこの症状には様々な原因が考えられます。
例えば、葉に黒いシミができる場合もあれば、葉焼けによる茶色い斑点とは異なる症状が出ることもあります。特に新芽が黒い状態は注意が必要です。
また、モンステラに黒すす病はつくのか、水切れしているサインはどのようなものか、といった疑問も浮かぶかもしれません。これらの原因を探り、適切な対処法を知ることが大切です。
対処法は夏と冬で異なる場合もあり、黒い葉っぱを切る際の切り方や、枯れた葉はどこから切るべきかを知っておく必要もあります。これはヒメモンステラでも同様です。
この記事では、モンステラの葉が黒くなる原因を突き止め、適切なケアで元気な姿を取り戻すための方法を詳しく解説します。
- モンステラの葉が黒くなる主な原因の特定方法
- 黒いシミや斑点、新芽の異常など症状別の見分け方
- 夏と冬、季節に応じた適切な対処法の違い
- 変色した葉の正しい剪定方法と復活のための管理術
モンステラの葉が黒くなる原因と症状

- 葉が黒くなる代表的な原因
- 水切れしているサインは?
- 新芽が黒いのは危険信号
- 葉にできる黒いシミの正体
- 葉焼けによる茶色い斑点との違い
- モンステラに黒すす病はつく?
葉が黒くなる代表的な原因

モンステラの葉が黒くなる現象は、植物からのSOSサインです。その背景には、いくつかの代表的な原因が隠されています。
多くの場合、これらの原因は単独ではなく、複合的に関わっていることもあります。
最も頻繁に見られる原因は「根腐れ」です。
これは、愛情ゆえに水をやりすぎたり、鉢の排水性が悪く土が常に湿った状態が続いたりすることで発生します。
モンステラの根も呼吸をしており、土中の水分が多すぎると酸素不足に陥ります。
結果として根が腐り始め、水分や養分を葉まで正常に運べなくなり、葉の先端や縁から黒く変色し、次第にブヨブヨと柔らかくなってきます。また、進行すると土から異臭がすることもあります。
次に考えられるのは「寒さによる凍傷」です。
モンステラは熱帯アメリカ原産の植物であり、寒さには非常に弱いです。
日本の冬、特に気温が10℃を下回る環境や、夜間に冷え込む窓辺に置いていると、葉の細胞内の水分が凍って組織が破壊され、凍傷を起こします。
この場合、葉は水っぽく黒ずみ、最終的には枯れてしまいます。
また、「葉焼け」も黒くなる原因の一つです。
本来、モンステラはジャングルの木漏れ日の下で育つため、強すぎる直射日光は苦手です。
夏場の強い日差しや西日に長時間さらされると、葉緑素が破壊され、最初は白っぽく色が抜け、次第に茶色くパリパリになります。
この症状がさらに進行・悪化すると、焦げたように黒っぽく変色することがあります。
他にも、「水切れ」が深刻な場合、根から最も遠い葉先まで水分が行き渡らず、乾燥によって黒くパリパリになることがあります。
また、良かれと思って与えた「肥料のやりすぎ(肥料焼け)」も、根にダメージを与え、結果として葉を黒く(または茶色く)変色させる原因となります。
これらの原因は、症状の現れ方や発生時期、土の状態などからある程度特定が可能です。
以下の表で、主な原因と症状の特徴、基本的な対策をまとめました。
主な原因と対策の早見表
| 主な原因 | 症状の特徴 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 根腐れ | 葉の縁や根元に近い部分から黒く、柔らかく(ブヨブヨ)なる。土から異臭がすることも。 | 水やりを控え、土を乾燥させる。風通しの良い場所に移す。ひどい場合は植え替えを行う。 |
| 寒さ(凍傷) | 葉全体または部分的に黒く、水っぽくなる。特に冬場や冷え込む窓際で発生しやすい。 | すぐに暖かい場所へ移動させ、最低10℃以上(できれば15℃)を保つ。冷気に当てない。 |
| 葉焼け(重度) | 直射日光により、最初は白〜茶色くパリパリになるが、進行すると黒っぽく焦げたようになる。 | レースカーテン越しなど、柔らかい光が当たる場所へ移動する。 |
| 水切れ | 葉先から黒く、乾燥してパリパリになる。同時に葉全体がしおれ、ハリがなくなる。 | 土の状態を確認し、乾いていたら鉢底から流れ出るまでたっぷり水を与える。 |
| 肥料焼け | 肥料を与えすぎた後、葉の縁から黒く(または茶色く)なる。根が傷んでいる可能性。 | 固形肥料なら取り除き、液体肥料なら水で肥料成分を洗い流す(洗肥)。しばらく施肥を休止する。 |
このように、葉が黒くなる原因は多岐にわたります。
土の状態、置き場所の温度や日当たり、水やりや肥料の頻度など、日頃の管理方法を総合的に見直し、どの原因に当てはまるかを冷静に突き止めることが、モンステラを救うための第一歩となります。
水切れしているサインは?

モンステラが水切れを起こしているかどうかは、いくつかの分かりやすいサインによって判断できます。植物は言葉を発せませんが、体全体で「水が足りない」という信号を送っています。
最も顕著な兆候は、葉のハリがなくなり、全体的にしおれて下を向くことです。
モンステラの葉は通常、ピンとしたハリを持っていますが、体内の水分が不足すると、葉からの水分の蒸散を抑えようとする防御反応として、葉が垂れ下がってきます。
水切れがさらに進行すると、根から最も遠い部分である葉の先端や縁から乾燥が始まります。
初期は黄色っぽく、やがて茶色くなり、最終的には黒くパリパリとした手触りに変わっていきます。
これは、水分が株の末端まで行き届かなくなっている証拠です。
これらの視覚的なサインと合わせて、土の状態を確認することが不可欠です。
鉢土の表面が乾いているだけでなく、指を第二関節(約3〜5cm)あたりまで差し込んでみても、土がカラカラに乾いて指に湿り気が感じられない場合は、水切れの可能性が非常に高いです。
また、プラスチック鉢などの場合は、鉢全体を持ち上げてみるのも有効な確認方法です。
水が十分に含まれている時に比べて、明らかに軽い場合も水分が不足している証拠となります。
注意:「根腐れ」との見極めが重要
ここで最も注意すべき点は、「根腐れ」との症状の類似性です。
前述の通り、根腐れを起こした場合も、根が機能不全に陥り水を吸い上げられなくなるため、結果として水切れと非常によく似た「葉がしおれる」症状が出ます。
この見極めのポイントは「土の湿り具合」です。
- 葉がしおれている + 土がカラカラに乾いている = 水切れ
- 葉がしおれている + 土がいつまでもジメジメ湿っている = 根腐れ
この判断を誤ると、根腐れしている株にさらに水を与えてしまい、症状を致命的に悪化させることになりかねません。
葉がしおれているのを発見した際は、必ず土の状態を確認する習慣をつけましょう。
新芽が黒いのは危険信号

モンステラから新しく出てくる、ドリルや筆の穂先のように巻かれた新芽が、開く前に黒くなってしまうのは、株が深刻なストレスを抱えていることを示す危険信号です。
新芽は人間でいう赤ちゃんのようなものであり、最も成長エネルギーを必要とするデリケートな部分です。
そのため、株本体や根に異常があると、その影響が真っ先に現れやすいのです。
主な原因としては、「根の異常」が強く疑われます。
長期間(一般的に2年以上)植え替えをしていない場合、鉢の中で根がぎゅうぎゅうに詰まる「根詰まり」を起こしている可能性があります。
根詰まりになると、新しい根を伸ばすスペースがなくなり、古い根が中心となって水分や養分の吸収効率が著しく低下します。
また、水のやりすぎや土の排水不良による「根腐れ」も同様です。根が腐敗し始めると、正常に機能しなくなり、株全体が栄養不足・水分不足の状態に陥ります。
これらの「根の異常」が発生すると、植物は新しい葉を展開させるための十分なエネルギー(水分や養分)を新芽に送ることができなくなります。
その結果、新芽は成長の途中で力尽き、黒く変色して枯れてしまうのです。
次に考えられる原因は、「寒さによるダメージ」です。
モンステラは低温に非常に弱く、特に冬場に冷気(窓からの隙間風やエアコンの直風など)にさらされると、新芽のような柔らかく保護されていない組織は簡単に凍傷を起こし、黒変してしまいます。
さらに、副次的な要因として、新芽が開く前にその隙間に水滴が溜まり、風通しが悪いことでそこから菌が侵入し、腐敗を引き起こすケースもあります。
これは特に、葉水(霧吹き)を頻繁に行う環境で、空気が滞留していると起こりやすいです。
もし新芽が黒くなってしまった場合、残念ながらその新芽が復活することはありません。
まずは以下の点を確認し、根本的な原因を取り除くことが求められます。
- 土の状態:
常に湿っていないか? 異臭はしないか?(根腐れのチェック) - 鉢底:
鉢底穴から根が大量にはみ出していないか?(根詰まりのチェック) - 置き場所:
冬場に窓際や玄関など、冷え込む場所に置いていないか?(低温障害のチェック) - 風通し:
部屋の隅などで空気が淀んでいないか?(蒸れ・腐敗のチェック)
原因が根詰まりや根腐れであると判断された場合は、株への負担が少ない生育期(気温が安定する5月〜9月頃)に、古い土を落として傷んだ根を整理し、新しい土で植え替える作業が必要になります。
葉にできる黒いシミの正体

モンステラの葉が、先端や縁から全体的に黒くなるのではなく、表面にポツポツとした「黒いシミ」や斑点がランダムに現れる場合、その主な原因は「病気」の可能性が考えられます。特にカビ(糸状菌)が原因となる病気が疑われます。
代表的な病気には「黒星病(黒点病)」や「斑点病」があります。
これらの病気は、特に気温と湿度が高くなる梅雨時や夏場に発生しやすい傾向があります。また、葉が密集して株内部の風通しが悪くなったり、水やりの際に葉に水がかかり、その水滴が長時間乾かずに残っていたりすると、カビの胞子が付着し、繁殖する好条件となってしまいます。
症状の具体的な特徴
- 黒星病(黒点病):
初期症状として、葉に針で刺したような黒い小さな斑点が現れます。この斑点は徐々に大きくなり、その周囲が黄色く変色していく(黄色い輪ができる)のが特徴です。 - 斑点病:
黒色や褐色の斑点が発生します。病状が進行すると、斑点の中央部分が白っぽく抜け落ち、最終的に穴が開くこともあります。
これらの病気によってできるシミは、葉焼けのように日光が当たった範囲が均一に変色するのとは異なり、局所的かつランダムに発生するのが大きな違いです。
対処法
もし、これらの病気と疑われる黒いシミを発見した場合、迅速な対処が必要です。
- 症状が出た葉の除去:
まず、感染拡大を防ぐために、シミが出ている葉を特定し、剪定して取り除くことが基本です。病気は他の健康な葉に伝染するため、被害が少ないうちに隔離します。 - 道具の消毒:
剪定に使用するハサミやナイフは、ウイルスや菌を他の部分に移さないよう、作業前後に必ず消毒してください。ライターの火で炙る、アルコール消毒液(エタノールなど)で拭く、熱湯をかけるといった方法が有効です。 - 環境の改善:
葉を取り除いた後は、株全体の風通しを良くするために、密集している他の葉も軽く剪定して整理します。 - 水やりの見直し:
再発を防ぐため、水やりは葉の上からかけるのではなく、株元の土に直接行うように心がけ、できるだけ葉が濡れたままになる時間を短くすることが大切です。
症状が広範囲に及んでいる場合は、市販の観葉植物用の殺菌剤(ダコニール、ベンレートなど)を散布することも検討しますが、まずは感染源の除去と環境改善が最優先となります。
葉焼けによる茶色い斑点との違い

モンステラの葉に現れる変色として、「葉焼けによる茶色い斑点(変色)」と「病気や根腐れなどによる黒いシミ」は、見た目や原因が大きく異なります。
これらの違いを正確に理解することは、誤った対処を防ぎ、適切なケアを行うために非常に不可欠です。
葉焼けによる茶色い斑点(変色)
葉焼けは、モンステラがその耐性を超えるほどの強い光、特に直射日光にさらされることで発生する生理障害です。
モンステラは本来、熱帯雨林の木々の下、木漏れ日が差すような環境で自生しています。
そのため、日本の夏場の強すぎる日差しや、一日中当たる西日などは非常に苦手です。
- 症状の進行:
- 初期症状として、葉緑素が破壊され、色が抜けたように白っぽく(または黄色っぽく)なります。
- 症状が進行すると、その部分は光合成ができなくなり、組織が壊死して茶色く変色します。
- 最終的には、水分が完全に失われ、触ると紙のようにパリパリに乾燥します。これが重度になると、焦げたように黒っぽく見えることもあります。
- 発生場所:
日光が最も強く当たる葉の表面や、窓に接している部分など、局所的に発生しやすいのが特徴です。 - 特徴:
色の変化は比較的均一で、斑点がじわじわと広がるというよりは、日光に「焼かれた」範囲が明確に出る傾向があります。
葉が黒くなる症状(黒いシミ・斑点)
一方で、葉が黒くなる症状は、前述の通り、根腐れ、寒さ(凍傷)、または病気が主な原因です。
- 症状の例:
- 根腐れ・寒さ: 葉の先端や縁から黒く変色し始めます。葉焼けと異なり、パリパリに乾燥するのではなく、組織が壊死して水っぽく柔らかくなったり、ブヨブヨしたりするのが大きな特徴です。
- 病気(黒星病など): 葉の表面に、原因不明の黒いシミや斑点がポツポツと発生します。しばしば、その周囲が黄色く縁取られることもあります。
- 特徴: 葉焼けが「乾燥・焦げ」という物理的なダメージであるのに対し、こちらは「腐敗・壊死」といった生物的・環境的なダメージによる症状と言えます。
見極めのチェックポイント
「これは葉焼け? それとも病気や根腐れ?」と迷ったときは、以下の3点を確認してください。
- 置き場所(日当たり):その場所は、直射日光が当たっていませんか?
- 土の状態:土はカラカラに乾いていますか? それとも常にジメジメしていますか?
- 季節(温度):: 今は冬で、窓際など寒い場所に置いていませんか?
これらの状況を総合的に確認することで、葉焼け(日光が原因)なのか、それ以外の問題(水や温度が原因)なのかを、より正確に判断できます。
モンステラに黒すす病はつく?

モンステラにも「黒すす病」が発生する可能性はあります。
ただし、この「黒すす病」という名称から誤解されがちですが、植物自体が直接引き起こす病気や、土壌の菌が原因となる病気ではありません。
黒すす病の正体は、「害虫の排泄物」に繁殖するカビです。
具体的には、「カイガラムシ」や「アブラムシ」といった、植物の樹液を吸う害虫(吸汁害虫)がモンステラに取り付くことが引き金となります。
これらの害虫は、植物から吸い取った樹液の糖分を多く含む、ベタベタとした排泄物を出します。
これが「甘露(かんろ)」と呼ばれるものです。この甘露が葉や茎の表面に付着し、それを栄養源として空気中に浮遊している黒いカビ(すす病菌)が次々と付着・繁殖します。
その結果、まるで葉の表面にすすを塗りつけたかのように黒くなってしまうのです。
モンステラは、比較的害虫に対して強い植物とされていますが、管理環境によっては害虫が発生します。
特に、室内で管理していて空気が乾燥していたり、風通しが悪い場所に置いていたりすると、カイガラムシなどが発生しやすくなるため注意が必要です。
症状の見分け方
葉が黒くなるといっても、根腐れや凍傷のように葉の組織自体が黒く壊死したり、ブヨブヨになったりするのとは全く異なります。
- 拭き取れる黒さ:
黒すす病の症状は、葉の表面に黒い「すす」や「粉」がこびりついているような見た目です。湿らせたティッシュや柔らかい布で優しくこすると、その黒い汚れが拭き取れるのが最大の特徴です。 - ベタつき:
葉や茎、さらには鉢の周りの床などがベタベタしている場合、それは害虫の排泄物(甘露)である可能性が非常に高いです。これは黒すす病の予兆、または既に併発している強力なサインと言えます。
対処法
もし黒すす病が確認されたら、対処の順序が重要です。
- 害虫の駆除 (最優先):
まず、根本原因であるカイガラムシやアブラムシを徹底的に駆除します。市販の殺虫剤(カイガラムシ専用のものなど)を使用するか、数が少ない場合は古い歯ブラシや綿棒などで物理的にこすり落とします。 - すすの拭き取り:
害虫を駆除した後、黒いすす自体を、濡らした布やティッシュで優しく拭き取ってください。
すす自体が直接モンステラを枯らすことは稀ですが、葉の表面を覆い尽くすことで光合成を著しく妨げます。
これにより、植物は必要なエネルギーを作れなくなり、徐々に生育不良に陥ってしまうため、早期の発見と対処が大切です。
モンステラの葉が黒くなる時の対処法

- 対処法は夏と冬でどう違う?
- 黒い葉っぱを切るときの切り方のコツ
- 枯れた葉はどこから切るべきか
- ヒメモンステラの葉が黒くなる場合
- まとめ:モンステラの葉が黒くなるのを防ぐには
対処法は夏と冬でどう違う?

モンステラの葉が黒くなる原因は、季節特有の環境ストレスと密接に関連しています。したがって、適切な対処法も季節によって大きく異なります。
夏と冬、それぞれの季節で特に注意すべき点と具体的な対策を解説します。
【夏の主な原因と対処法】
夏に葉が黒くなる(または茶色く焦げる)場合、最も多い原因は「葉焼け」と「高温多湿による蒸れ(根腐れ)」です。
- 葉焼け対策(光の管理):
夏の直射日光は、植物にとって非常に過酷です。室内であっても、窓ガラス越しに差し込む強い光が長時間当たると、モンステラの葉は簡単に葉焼けを起こし、茶色く、ひどい場合は黒く焦げてしまいます。- 【対策】
すぐに直射日光が当たらない場所へ移動させます。レースカーテン越しの柔らかい光が当たる「明るい日陰」がモンステラにとっての理想的な環境です。もし適切な移動先がない場合は、窓に遮光ネットを張るなどして、光量を調整してください。
- 【対策】
- 蒸れ・根腐れ対策(水と風の管理):
夏は気温が高く土が乾きやすいため、水やりの頻度も自然と上がります。しかし、同時に湿度も高くなるため、風通しが悪いと鉢の中が常に湿った状態になり、高温多湿で「蒸れ」てしまいます。これは根腐れを引き起こす最悪の環境であり、結果として根がダメージを受けて葉が黒くなることがあります。- 【対策】
水やりは、土の表面がしっかり乾いたことを指で確認してから行います。受け皿の水は必ず捨ててください。また、エアコンやサーキュレーターを使って室内の空気を意識的に動かし、鉢周りの風通しを確保することが非常に大切です。
- 【対策】
【冬の主な原因と対処法】
冬に葉が黒くなる場合、その原因のほとんどが「寒さによる凍傷」と「水のやりすぎによる根腐れ」です。
- 寒さ対策(温度の管理):
熱帯植物であるモンステラは寒さに極めて弱く、生育を維持するには最低でも10℃以上、できれば15℃程度をキープするのが理想です。特に夜間は、窓辺の気温が外気とほぼ同じくらいまで急激に下がります。この冷気にさらされると、葉は「凍傷」を起こし、水っぽく黒く変色してしまいます。- 【対策】
夜間は必ず窓から離れた部屋の中央などに鉢を移動させてください。段ボールや発泡スチロールの箱で鉢を囲ったり、不織布(保温シート)を株全体にふんわりとかけたりするのも有効な防寒対策です。
- 【対策】
- 根腐れ対策(水の管理):
冬は気温が低いため、モンステラの成長は非常に緩慢になります(休眠期に近い状態)。そのため、水を吸い上げる力も夏に比べて著しく弱まります。夏と同じペースで水やりを続けると、土がまったく乾かず、常に湿った状態が続いてしまいます。冷たい水がずっと根に触れている状態は、最も根腐れを起こしやすい危険な状態です。- 【対策】
冬の水やりは、回数を大幅に減らします。土の表面が乾いてから、さらに2~3日(あるいは1週間近く)待つくらい、乾燥気味に管理するのが成功のコツです。また、水やりをする際は、冷たすぎる水道水ではなく、室温に戻した水を与えるようにしましょう。
- 【対策】
このように、夏は「強すぎる日差しと蒸れ」、冬は「寒さと水のやりすぎ」という、季節ごとに全く異なる要因に注意を払う必要があります。
それぞれの季節に合わせた管理方法に切り替えることが、葉が黒くなるのを防ぐ最大の鍵となります。
黒い葉っぱを切るときの切り方のコツ

葉が一度黒くなってしまった場合、残念ながらその部分が元の緑色に戻ることはありません。
変色した部分は光合成ができず、見た目を損ねるだけでなく、病気の場合は感染源となる可能性もあるため、剪定(カット)することが推奨されます。
切り方には、症状が葉の一部か全体かによって、適切な方法があります。
作業前には、ハサミをアルコールで拭いたり、火で軽く炙ったりして「消毒」することを強くおすすめします。これにより、切り口から雑菌が入るのを防ぎます。
1. 葉の一部だけが黒い場合(葉先・縁など)
葉先や縁だけが黒くなっているなど、症状が部分的であり、葉の大部分がまだ健康な緑色を保っている場合は、葉全体を切り取る必要はありません。
- 切り方:
清潔なハサミを使い、黒くなった部分だけを切り取ります。この時、黒い変色部分と健康な緑色の部分の境目ギリギリで切るのではなく、緑色の健康な部分を1〜2mm程度含めて切ることがポイントです。こうすることで、切り口から再び変色が広がるのを防ぐ効果が期待できます。 - 見た目への配慮:
モンステラの特徴的な葉の形を損なわないよう、元の葉の丸みや切れ込みのカーブをイメージしながらカットすると、剪定した跡が目立ちにくくなります。直線的にバッサリ切るよりも、手間はかかりますが仕上がりが自然です。
2. 葉の大部分または全体が黒い場合
葉の半分以上が黒くなってしまった場合や、葉の付け根(葉柄)まで変色が及んでいる場合は、その葉自体を付け根から取り除きます。
株の体力を温存させるためにも、思い切って剪定しましょう。
- 切り方:
葉柄(ようへい:葉と太い幹をつなぐ細い茎)を、幹(太い茎)の付け根から切り取ります。「どこから切るべきか」と迷うかもしれませんが、葉柄を中途半端な位置で切ると、残った部分が結局枯れ込み、そこから菌が侵入するリスクがあるため、幹の生え際(節)からきれいに取り除くのが最も望ましいです。幹本体や、そこから出ようとしている新芽や気根を傷つけないよう、慎重にハサミを入れてください。
剪定時の注意点:樹液による「かぶれ」
モンステラを含むサトイモ科の植物は、茎や葉を切ると白い樹液が出ることがあります。この樹液には「シュウ酸カルシウム」という成分が含まれています。
これは皮膚に触れると、目に見えないほどの細かい針状の結晶が刺さり、強いかゆみや炎症、かぶれを引き起こす可能性があります。特に肌が敏感な方は注意が必要です。
剪定作業の際は、必ず園芸用の手袋(ゴム手袋など)を着用してください。もし樹液が皮膚についてしまった場合は、こすらずにすぐに水でよく洗い流してください。
どちらの場合も、剪定後は株の様子をよく観察し、切り口が早く乾くよう、風通しの良い場所で管理することが大切です。
枯れた葉はどこから切るべきか

前述の通り、黒くなってしまった葉や、水切れ・寿命などで完全に枯れてしまった葉は、光合成もできず、元に戻ることはありません。
これらを放置しておくと、見た目が悪いだけでなく、風通しを悪化させ、カビや病害虫の温床になる可能性があります。
また、株のエネルギーを無駄に消費させてしまうことにも繋がるため、早めに剪定するのが賢明です。
切るべき場所は、その葉や茎がどの程度枯れているかによって決まります。
1. 葉(葉柄)だけが枯れている場合
葉全体が黒く、または茶色くパリパリに枯れてしまっているものの、幹(太い茎)はまだ緑色で健康な場合です。これが最も一般的なケースです。
- 切る場所:
その葉を支えている「葉柄(ようへい)」の付け根から切り取ります。葉柄とは、葉本体と太い幹(茎)をつないでいる細い茎の部分です。 - 切り方:
この葉柄を、幹の生え際ギリギリでカットします。中途半端に葉柄を残してしまうと、その残った部分が結局枯れ込み、そこから菌が侵入して幹本体まで傷めてしまう原因にもなりかねません。清潔で切れ味の良いハサミやナイフを使い、幹本体を傷つけないように注意しながら、できるだけ付け根からきれいに切り落としてください。
2. 幹(茎)自体が枯れている場合
根腐れや病気、あるいは深刻な寒さのダメージにより、葉だけでなく幹(茎)の一部が黒くブヨブヨと腐敗したり、茶色くスカスカになって枯れたりしている場合もあります。これはより重篤な状態です。
- 切る場所:
枯れた部分を完全に取り除く必要があります。黒く変色している部分と、まだ緑色で健康な部分の境目を見極めます。そして、病気の進行を食い止めるため、必ず健康な組織が残るよう、枯れた部分よりも少し下(根に近い側)で茎をカットします(切り戻し剪定)。 - 切り方のコツ:
このとき、モンステラの茎には「節(ふし)」と呼ばれる、葉や気根が出ていた跡の膨らんだ部分があります。ここは「成長点」でもあり、新しい芽を出す力を持っています。可能であれば、この節の少し上(1〜2cm程度)で切ると、その節から新しい脇芽が伸びてきて、株が再生する可能性が高まります。
いずれの場合も、剪定に使用する道具は必ず消毒(アルコール消毒や火での炙り)を行ってください。
特に幹を切った場合は切り口が大きくなるため、雑菌の侵入を防ぐためにも、作業後は風通しの良い場所で管理し、切り口をしっかりと乾燥させることが非常に重要です。
ヒメモンステラの葉が黒くなる場合

「ヒメモンステラ」という名前で流通している植物には、主に「ラフィドフォラ・テトラスペルマ」や、「モンステラ・アダンソニー(マドカズラ)」の小型種などが含まれます。
これらは、一般的なモンステラ(デリシオーサ)と近縁、あるいは似た性質を持つため、葉が黒くなる場合の原因と対処法も基本的に同じです。
しかし、ヒメモンステラはその特性上、いくつかの点でトラブルが起きやすい側面も持っています。
ヒメモンステラ特有の注意点
- 根詰まりしやすい:
ヒメモンステラは成長速度が早い品種が多く、またデリシオーサに比べて小さめの鉢で管理されることが多いため、鉢の中で根がすぐにいっぱいになる「根詰まり」を起こしやすい傾向があります。根詰まりは水分や養分の吸収を妨げるため、葉先が黒くなったり、新芽が黒いまま枯れたりする直接的な原因となります。 - 葉焼けしやすい:
品種にもよりますが、葉がデリシオーサよりも小さく薄い傾向があるため、強い日差しに対する耐性がやや低い場合があります。直射日光に当たると、より速く葉焼けを起こし、黒く(茶色く)焦げてしまうことがあります。 - 水の管理がデリケート:
鉢が小さいということは、土が保持できる水分量も少ないことを意味します。そのため、水切れを起こしやすい一方で、水を与えすぎるとすぐに過湿になり「根腐れ」も起こしやすいという、デリケートな水分管理が求められます。
主な原因と対処法
したがって、ヒメモンステラの葉が黒くなった場合、まずは以下の3大原因を疑います。
- 根腐れ(水のやりすぎ):
鉢土が常に湿っていませんか? 小さな鉢だからと毎日水を与えていると、過湿になりがちです。土が乾いてから水を与えるという基本は同じです。 - 寒さ(低温障害):
一般的なモンステラ同様、寒さには非常に弱いです。冬場に10℃以下の環境、特に冷たい窓辺などに置いていないか確認してください。 - 根詰まり:
最後に植え替えたのはいつですか? 鉢底から根がはみ出していたり、水の染み込みが悪くなっていたりしたら、根詰まりのサインです。
対処法もモンステラに準じます。
まずは、土の湿り具合、置き場所の温度、日当たりを徹底的にチェックしてください。黒くなってしまった葉は、清潔なハサミで付け根からカットします。
そして、根腐れや根詰まりが強く疑われる場合は、株の生育期(春〜秋の暖かい時期)を選んで、古い根や傷んだ根を整理し、一回り大きな鉢に植え替えることを検討してください。
ヒメモンステラは、その小ぶりな見た目から繊細な印象を受けるかもしれませんが、葉が黒くなるトラブルの根本的な原因は、一般的なモンステラと共通していることがほとんどです。
基本的な管理方法を見直すことで、多くの場合、改善が見込めます。
まとめ:モンステラの葉が黒くなるのを防ぐには
モンステラの葉が黒くなるというトラブルは、多くの原因が考えられますが、そのほとんどは日々の管理方法を見直すことで予防・改善が可能です。
最後に、モンステラを健康に育て、葉が黒くなるのを防ぐための重要なポイントをまとめます。
- 葉が黒くなる主な原因は「根腐れ」「寒さ」「葉焼け」「水切れ」「病害虫」
- 最も多い原因は「水のやりすぎ」による根腐れ
- 水やりは土の表面がしっかり乾いてから行う
- 受け皿に溜まった水は必ず捨てる
- 冬は水やりの頻度を減らし、乾燥気味に管理する
- モンステラは寒さに弱く、最低10℃以上を保つ
- 冬は窓際の冷気を避け、部屋の暖かい場所に置く
- 夏の直射日光は「葉焼け」の原因になるため避ける
- レースカーテン越しの明るい日陰が最適な置き場所
- 葉がしおれ、土が乾いているのは「水切れ」のサイン
- 土が湿っているのにしおれる場合は「根腐れ」を疑う
- 新芽が黒いのは「根詰まり」や「根腐れ」のサイン
- 葉に「黒いシミ」ができる場合は病気の可能性を疑う
- 「黒すす病」はカイガラムシなどの排泄物が原因で発生する
- 黒くなった葉は元に戻らないため、清潔なハサミで剪定する
- 葉の部分的な変色は、変色部より少し内側をカットする
- 葉全体が枯れた場合は、葉柄の付け根からカットする
- ヒメモンステラも同様の原因で葉が黒くなる
関連記事はこちら!