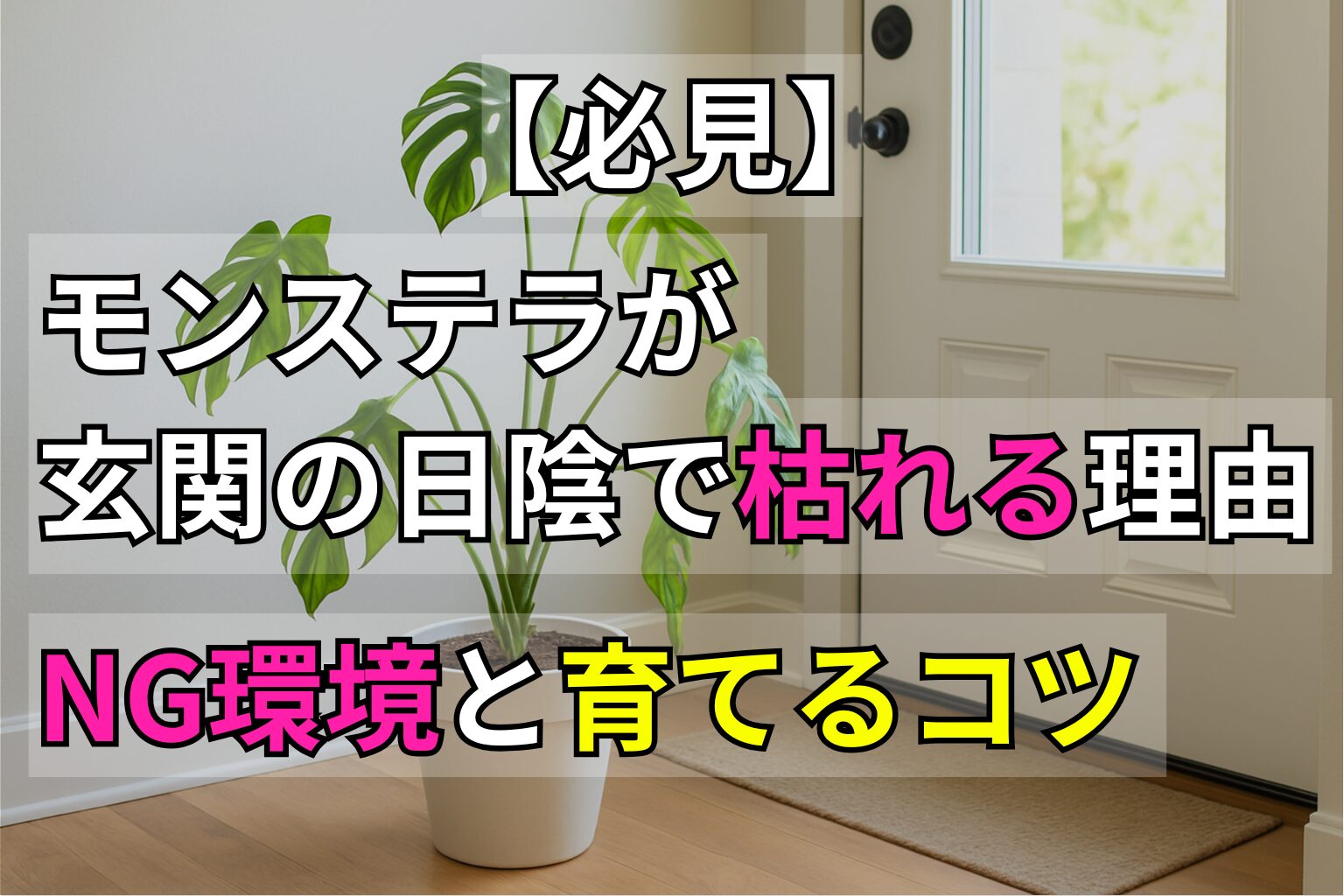こんにちは。「観葉植物の育て方ナビ」運営者のmomoです。
おしゃれな観葉植物の代表格、モンステラ。そのユニークな葉の形は、空間を一気にセンスアップしてくれますよね。
家の顔である玄関に置けたら素敵だな、と思う方も多いんじゃないでしょうか。
ですが、ご存知の通り、玄関は日陰になることが多く、「こんな暗い場所で本当に育つのかな?」「日光不足ですぐに枯れるんじゃないか…」と不安に感じている方も多いかもしれません。
また、モンステラは風水的に良いとも聞きますが、暗い玄関に置いてもその効果がちゃんとあるのか気になるところです。
それに、日陰だと水やりの頻度もわからなくなるし、特に寒い冬越しの問題もありますよね。
そこでこの記事では、モンステラが玄関の日陰という少し特殊な環境にどれくらい耐えられるのか、その「適性」のホントのところから、暗い玄関でも元気に育てるための具体的な管理のコツや注意点まで、私の経験も踏まえて詳しく解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
- モンステラが「日陰に強い」の本当の意味
- 暗い玄関で育てるための必須アイテムと環境づくり
- 根腐れや害虫を防ぐ日陰での繊細な管理術
- 見落としがちな冬越しや風水効果のポイント
モンステラは玄関の日陰に置ける?

さて、核心のテーマですが、おしゃれなモンステラ、家の顔である玄関に飾りたいですよね。
でも、日陰や暗さが心配…。SNSなどでは素敵に玄関に置かれている写真も見かけますが、実際に自分の家でうまくいくかは別問題です。
ここでは、まずモンステラが玄関の環境に適しているのか、その「適性」について、少し踏み込んで一緒に見ていきましょう。
これを理解するだけで、失敗する確率はぐっと減らせると思いますよ。
「耐陰性=暗くても育つ」の誤解
よく「モンステラは耐陰性があるから日陰でも大丈夫」と聞きますが、これ、実はかなり誤解を生みやすい表現かなと思います。
モンステラの「耐陰性」というのは、「暗い場所でも元気に育つ」という意味ではなく、「真夏の強すぎる直射日光が苦手(=葉焼けしやすい)」という意味合いが強いんです。
もともと熱帯のジャングルで、他の大きな木々の下、木漏れ日を浴びて育っている植物なんですね。
なので、モンステラが一番好きなのは「レースカーテン越しのやわらかい光が入る、明るい日陰」です。リビングの窓際や、北向きの窓辺などが理想的です。
暗すぎる場所のリスク(光合成ができない)
植物には「光補償点(こうほしょうてん)」といって、生存維持(呼吸するだけ)に必要な最低限の光の量があります。
これを下回る暗さ(例えば窓のない閉鎖的な玄関など)では、光合成で得られるエネルギーより呼吸で消費するエネルギーが上回ってしまいます。
そうなると、植物は自分が蓄えた養分を切り崩しながら生きることになり、ゆっくりと弱っていってしまいます。
その結果、光を求めて茎だけがひょろひょろと伸びる「徒長(とちょう)」という状態になったり、モンステラの最大の魅力である葉の「切れ込み」が入らなくなったりするんです。
 momo
momo何を隠そう、私もモンステラを育て始めた頃、この『耐陰性』という言葉を信じて、窓のない玄関に置いてみたことがあるんです。
確かに枯れはしないのですが、新しく開く葉が、いつまで経っても切れ込みのないツルツル(ハート型)のままで…。
『あれ?うちの子はいつになったら割れるんだろう?』と、ずっと首をかしげていました。
あれがまさに『光量不足』のサインだったんですね。
置ける玄関と置けない玄関の差
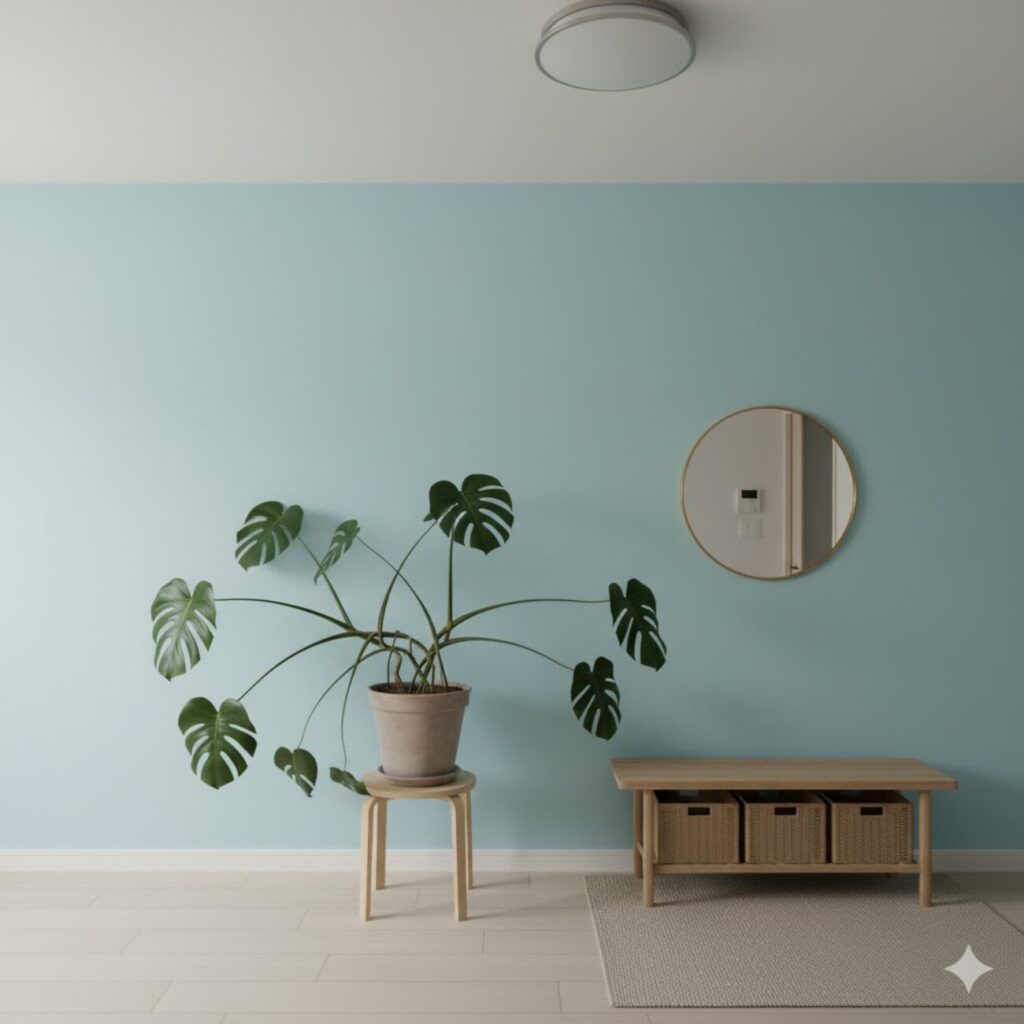
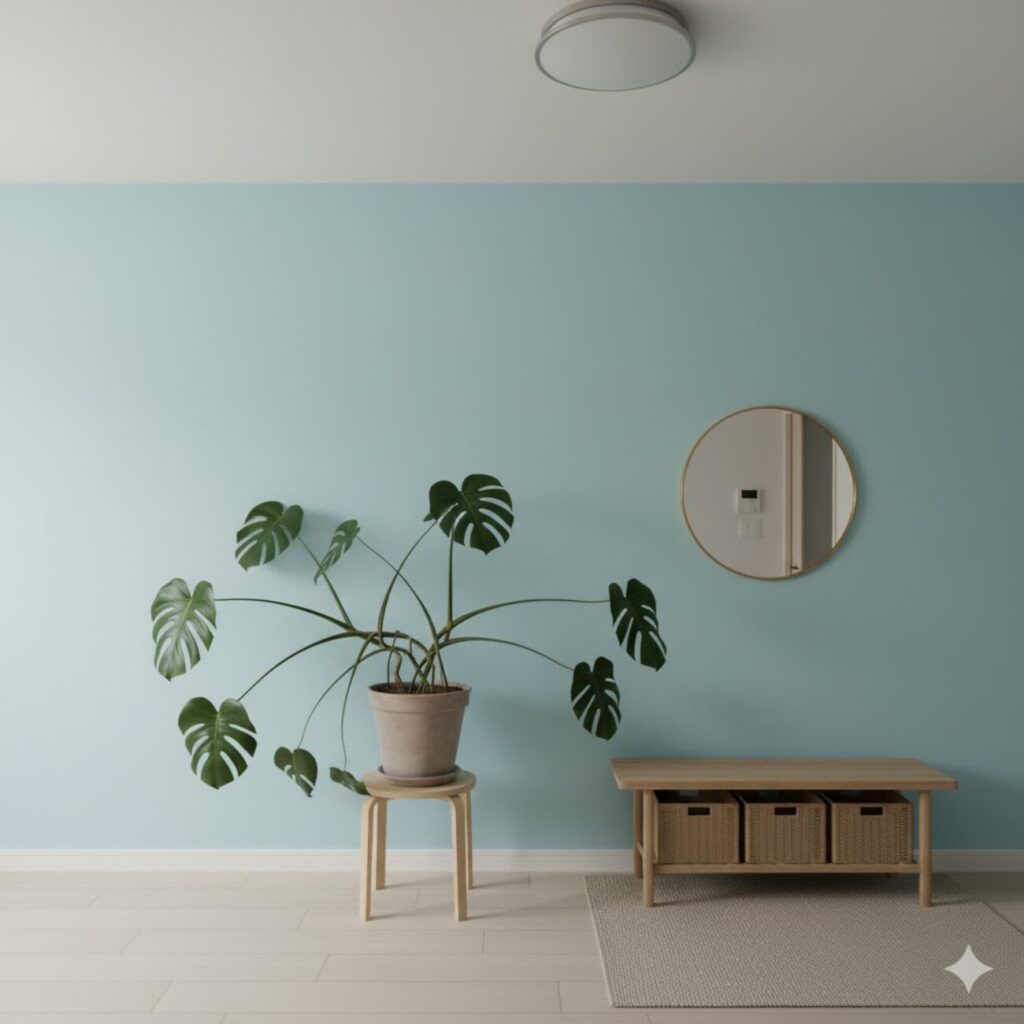
とはいえ、すべての玄関がNGというわけではありません。「明るい玄関」と「暗い玄関」には、植物にとって天と地ほどの差があります。
例えば、日中、照明をつけなくてもなんとなく明るい玄関(リビングの光が届く、吹き抜けがあるなど)と、日中でも照明が必須な玄関とでは、環境がまったく違いますよね。
明るさの目安(感覚と照度)
専門的な話になりますが、明るさは「ルクス(照度)」という単位で測ります。
一般的な観葉植物が元気に成長するには、最低でも500〜5,000ルクス程度は必要とされています。
農林水産省HP「屋内緑化マニュアル」によると、モンステラは最低500ルクス程度の明るさが生育に必要とされていて、一般的な観葉植物とくらべると耐陰性が高いことがわかります。
しかし、窓のない暗い玄関は、私たち人間が生活するには十分な明るさ(200〜500ルクス程度)であっても、モンステラをはじめとした植物の生育ライン(光補償点以上)には達していない可能性が非常に高いです。
「生存維持」すら難しいレベルの暗さ、ということも珍しくありません。
ちなみに、ルクスの各数値ごとの明るさの目安については、以下のとおりと言われています。
| ルクスの数値 | 使用例 | 目安 |
|---|---|---|
| 100 lx | 暗めの室内照明や間接照明 | リラックスした雰囲気に最適 |
| 500 lx | オフィスや教室、作業場の照明 | 快適に作業や勉強ができる明るさ |
| 1000 lx | 曇りの日の屋外やしっかりとした照明のオフィス | 屋外や広い室内空間の明るさ |
上の表から、一般的な玄関の明るさは100~500ルクスの間であることが推測できるため、備え付けの照明だけではモンステラの生育最低ラインを超えるのは難しいと考えられます。
でも、諦めるのはまだ早いです。この問題は、人工的な補助光を利用すれば解決できます。
最近では観葉植物の育成用のLEDライトも販売されているため、モンステラ育成のために玄関に設置すると良いでしょう。
スマホアプリで簡易チェックも
最近はスマートフォンの無料アプリで「照度計(ルクスメーター)」が使えるものもあります。プロ用の機材とは違うのであくまで簡易的な目安ですが、ご自宅の玄関がどのくらいの明るさなのか、一度測ってみるのも面白いかもしれませんよ。「こんなに暗かったんだ!」と驚くことも多いです。



私もこの記事を書くにあたって、自宅の玄関をスマホアプリで測ってみたんです。
自分では『日中はまあまあ明るいかな?』と思っていた場所が、なんと300ルクスしかなくて…。
植物にとっては『ほぼ真っ暗』だったんだなと、本当に驚きました(笑)。
暗い玄関に潜む3つのリスク
実は、玄関は植物にとって室内でもかなり過酷な環境のひとつなんです。
光不足だけでなく、主に3つのリスクが常に存在し、これらが連鎖することでモンステラを弱らせてしまいます。
1. 光不足
これは先ほどお話しした通りですね。光合成が不十分になることで、徒長や葉の切れ込み不足の直接的な原因になります。
また、光が足りないと植物自体の活力が落ちるため、病気や害虫への抵抗力も弱まってしまいます。
2. 極端な温度変化
玄関は外気の影響を最も受けやすい場所です。
ドアの開閉による隙間風などで、冬は急激に温度が下がりやすくなります。
逆に夏は、空気の逃げ場がないために「熱だまり」ができ、風通しが悪く蒸し暑くなることも…。
この激しい寒暖差は、熱帯植物であるモンステラにとって大きなストレスになります。
3. 風通しの悪さ
空気が停滞しやすく、湿気がこもりやすいのも玄関の大きな特徴です。
これが、モンステラを枯らす2大要因である「根腐れ」と「害虫」の根本的な原因になってしまいます。
風通しが悪いと土がなかなか乾かず、常に湿った状態が続きます。
これは根が呼吸できなくなる「根腐れ」に直結しますし、湿った環境を好むコバエや、空気がよどむと発生しやすいハダニなどの温床にもなってしまいます。
負の連鎖に注意
「光不足で生育が鈍る」→「土が乾きにくくなる」→「風通しが悪いためさらに乾かない」→「根腐れを起こす」→「冬の低温でとどめを刺される」…これが暗い玄関での典型的な失敗パターンです。
玄関の風水効果と健康状態


玄関にモンステラを置きたい理由として、「風水効果」を期待している方も多いと思います。
せっかく置くなら、運気もアップしたいですよね。
風水で玄関は「気の入り口(龍の口)」とされ、すべての運気が入ってくる場所。
そこに生命力あふれる観葉植物を置くことは、良い気を呼び込み、悪い気を浄化するラッキーアイテムとされています。
モンステラは観葉植物の中でも特に人気で、
- 金運アップ:その丸みを帯びた大きな葉が「お金を包み込む」といわれる。
- 対人運・家庭運:人をリラックスさせ、穏やかな気で家庭内の調和を促す。
- 希望の光(魔除け):象徴的な葉の「切れ込み」から希望の光が差し込む、または悪い気を払うといわれる(ハワイでは神聖な植物とされていますね)。
など、とても縁起の良い植物として知られています。
ただし、健康な株であることが大前提!
風水で最も重要とされているのは、「植物が健やかに成長していること」だそうです。
もし暗い玄関に放置して、光不足でひょろひょろになったり、寒さで葉が黒ずんだり、水のやりすぎで根腐れを起こしているような状態だと…。
かえって悪い気を溜め込んでしまう「陰の気」の発生源になるとも言われています。
風水効果を最大限に引き出すためにも、まず第一にモンステラが元気に育つ環境(特に「光」と「風」)を整えてあげることが大切ですね。
寒い玄関はNG?冬越しの注意点
モンステラは熱帯の植物なので、やっぱり寒さには弱いです。これは非常に重要なポイントです。
安全に冬越しさせるための温度ラインは、最低でも10℃以上をキープしたいところ。
できれば15℃あると安心です。耐えられる限界(生育が止まる)が5℃前後と言われますが、これを下回ると、株が弱って「低温障害」を起こし、葉が黒ずんで枯れてしまう可能性があります。
外気の影響を受けやすい玄関は、特に断熱性の低い家屋や寒冷地の場合、冬の夜から早朝にかけて、この「5℃」を簡単に下回ってしまう危険な場所なんです。
最善策は「冬だけ避難」
正直なところ、モンステラの冬越し対策としては、冬の間だけは玄関から出して、1日を通して10℃以上を保てる暖かいリビングなどに避難させてあげるのが一番安全で、おすすめです。
もし移動できない場合の対策
どうしても移動が難しい場合は、次善策としてできる限りの保温対策をしてあげてください。
- 置き場所:冷気が直接当たるドアや窓際、コンクリートの床に直接置くのを避ける。(少し高さのある台や棚の上、玄関の中でも奥まった場所に)
- 鉢の保温:冷気は下から来るため、鉢ごと発泡スチロールの箱に入れるのが非常に有効です。また、鉢の周りに毛布やプチプチ(緩衝材)を巻くだけでも違います。
- 株の保温:夜間だけ、不織布やビニールを株全体にふんわりとかけてあげる(霜よけのイメージですね)。
モンステラを玄関の日陰で育てるコツ


玄関の環境リスクがわかったところで、次は「じゃあ、どうすれば玄関の日陰でもモンステラを元気に育てられるの?」という具体的な管理方法(コツ)について、詳しく解説していきますね。
暗い玄関には育成ライトが必須


「日中でも照明が必須」なレベルの暗い玄関でモンステラを元気に育てるなら、先述のとおり、これはもう「植物育成ライト」(LEDライト)が必須アイテムだと私は思います。
これは「あったら良いな」ではなく「ないと無理」というレベルです。
これが、光量不足を解消する唯一かつ最善の解決策です。
育成ライトさえあれば、光不足による徒長や、葉の切れ込みが入らないといった問題は、ほぼ解決できますよ。
ライトの選び方と使い方
- 種類:最近は安価で高性能な「LEDタイプ」が主流です。電気代も安く、熱も持ちにくいので植物に近づけても安心です。太陽光に近い波長を再現した「フルスペクトル」と書かれたものがおすすめ。
- 形状:スポットライト型、バー(棒)型、クリップ型など色々あるので、玄関のスペースやモンステラの大きさに合わせて選びましょう。
- 使い方:タイマー付きのコンセントを使って、植物の生活リズムを作るためにも、1日に8〜12時間程度、光を当ててあげるのが目安です。夜通し点けっぱなしは逆効果になることもあるので注意してくださいね。
「日光浴」での管理はかなり大変…
ライトを設置できない場合の次善策として、週に数回、明るい場所に移動させて「日光浴」させる方法もあります。
ただ、これには大きな注意点が2つあります。
- 植物のストレス:植物は環境の変化に敏感です。暗い玄関と明るいリビングを頻繁に行き来させることは、それ自体が大きなストレスになる可能性があります。
- 葉焼けのリスク:日陰に慣れたモンステラを急にベランダなどに出し、直射日光に当てると、葉が真っ黒に焼けてしまう「葉焼け」を即座に起こします。移動先は必ず「レースカーテン越し」などの明るい日陰にしてくださいね。
安定した環境で管理できる育成ライトの方が、植物にとっても人にとっても負担が少ないかなと思います。
日陰の水やりと根腐れ対策
日陰管理での最大の失敗原因が、この「水のやりすぎによる根腐れ」です。
水やりの基本は「土の表面が乾いたら、鉢底から水が出るくらいたっぷり」ですが、日陰で風通しの悪い玄関は、リビングなどに比べて圧倒的に土が乾くのが遅いんです。
明るいリビングなら1週間で乾く土も、暗い玄関では2週間、3週間と乾かないことも普通にあります。



これは本当に多くの方が失敗してしまうポイントで、私も初心者の頃にこれでいくつも枯らしてしまいました…。
特に玄関に置いたモンステラに『暗い場所でかわいそうに…』と、良かれと思ってお水をこまめにあげていたんです。
でもある日、なんだか葉っぱが黄色いな?と思って鉢を持ち上げたら、受け皿に水が溜まったままで…。
慌てて鉢から抜いたら、案の定、根が真っ黒に…なんて苦い経験があります。
これはNG!根腐れを招く水やり
- 「1週間に1回」など、カレンダー通りの水やり(土が湿っているのに与えてしまう)
- 「毎日少しずつ」と、常に土を湿らせる水やり(土の中が乾く暇がない)
- 土が乾いているか確認しないでの水やり
光が当たらず(蒸散が少ない)、風通しも悪いと、土がずっと湿った状態が続き、根が呼吸できなくなって窒息し、腐ってしまいます。
これが根腐れのメカニズムです。
土の乾き具合の確認方法
日陰では、土の表面が乾いて見えても、鉢の中(特に中心部)はまだ湿っていることが多いです。
水やり前には必ず土の中の湿り気を確認しましょう。
- 指で確認:土の表面から数cm下まで指を入れ、土を触ってみて水分の感触がなくなったら。
- 割り箸で確認(おすすめ):乾いた割り箸を鉢の奥まで(鉢底近くまで)差し込み、数分待ってからゆっくり引き抜きます。
- 箸が湿っている・土が付着する → まだ湿っています。水やりは絶対に見送ります。
- 箸が乾いている・土が付かない → 土の中が乾いています。水やりのタイミングです。
- 鉢の重さで確認:水やり直後の重さを覚えておき、軽くなったら乾いたサイン。これは慣れが必要ですが、一番確実かもしれません。



指や見た目だけだと私も不安なので、いつも使い古しの菜箸を『モンステラ専用チェック棒』にして、水やりの前に必ず土の奥までブスッと刺して確認しています(笑)。
これで湿った土が付いてこなければOK、という感じです。
受け皿の水は「即」捨てる
そして、水やり後、受け皿に溜まった水は必ず即座に捨ててください!これを溜めたままにするのは、鉢底が常に水に浸かった状態(=底面給水状態)になり、根腐れの大きな原因になりますよ。
玄関のコバエや害虫を防ぐには
玄関の「よどんだ空気」と「乾きにくい土」は、残念ながら害虫にとって快適な環境になってしまいます…。
サーキュレーターの活用がおすすめ
対策として一番有効なのは、サーキュレーターや小型扇風機を使って、玄関の空気を強制的に動かす(循環させる)ことです。
首振り機能で、緩やかな風を植物の周りに送ってあげましょう。
これだけで土の表面が適度に乾きやすくなり、害虫の予防に絶大な効果がありますよ。空気が動く場所を嫌う害虫も多いです。
日陰で発生しやすい害虫と対策
特に注意したいのは以下の3種類です。
- ハダニ
- 症状:葉の裏に寄生し、葉の栄養を吸います。非常に小さく(0.5mm程度)、肉眼では点にしか見えません。症状が進むと葉の色が白っぽく「かすれた」ようになります。
- 原因:高温・乾燥した環境、よどんだ空気を好みます。
- 対策:ハダニは水を嫌うので、こまめに霧吹きで葉に水をかける「葉水(はみず)」(特に葉の裏側!)が予防と初期駆除に有効です。
- カイガラムシ
- 症状:葉や茎に白い綿や茶色い硬い殻のように付着します。ベタベタした排泄物(すす病の原因)を出すことも。
- 原因:風通しが悪い、暗いと発生しやすいです。
- 対策:見つけたら歯ブラシや綿棒、ティッシュなどで物理的にこすり落とすのが早いです。数が多い場合は専用の殺虫剤が必要になります。
- コバエ(キノコバエ類)
- 症状:植物の周りを小さなハエが飛び回ります。
- 原因:湿った土や有機質肥料を好み、土の中に卵を産み付けます。
- 対策:根本原因は「水のやりすぎ」であることが多いです。水やり頻度を見直し、土の表面を乾燥気味に保つことが最大の対策です。受け皿の水を放置しないことも重要です。
「葉水」と「乾燥」の矛盾を解決
ここで「ハダニ対策には『葉水(加湿)』が有効だけど、コバエや根腐れは『湿気』を好む…」という矛盾が生じますよね。
この解決策が、まさに「サーキュレーターで空気を循環させる」ことです。
サーキュレーターで空気(と土の表面)は動かしつつ、葉水で「葉」の湿度だけは保つ。これが日陰管理の理想的な形かなと思います。
葉が黄色い・黒いときのSOS
玄関でモンステラの様子がおかしくなった時のトラブルシューティングです。
葉は植物の健康状態を教えてくれる大事なサインです。早めに気づいて対処しましょう。
葉が黄色い
原因は多岐にわたりますが、玄関でチェックすべきは「土の状態」と「季節」です。
- 土がずっと湿っている状態で黄色くなった:
「根腐れ」か「寒さ(低温障害)」を強く疑います。土の匂いを嗅いでみて、腐敗臭やカビ臭がしたら根腐れの可能性大です。早急な植え替えが必要かもしれません。 - 土がカラカラに乾いて黄色くなった:
これは単純な「水切れ」です。日陰でも長期間放置すれば水は切れます。 - 下葉(古い葉)から順番に黄色くなった:
「新陳代謝」による自然な老化現象の場合もあります。
関連記事:モンステラの黄色くなった葉はどうするべき?症状別の原因と対処法を解説
葉先やフチが茶色くパリパリ
これは「肥料焼け(肥料のやりすぎ)」か、エアコンの風が直撃するなどの「急な乾燥」が原因かもしれません。
日陰での肥料は「控えめ」が鉄則
日陰に置く場合、光合成が少ないため、モンステラの生育はとてもゆっくりになります。そういう時に肥料(特に化成肥料)を規定量与えてしまうと、植物が成分を吸収できずに土壌内に蓄積し、根を傷めてしまう「肥料焼け」を起こしやすいんです。
日陰管理の場合、肥料は生育期(5月〜9月)であっても、規定量よりさらに薄め(通常の2倍以上に希釈)にするか、新芽が動いているなど明確な成長が見られる時だけあげるのが安全です。冬の肥料は厳禁ですよ!
葉に黒いシミが広がる
冬越し中にこの症状が出たら、ほぼ間違いなく「寒さ」による低温障害です。
葉の細胞が凍って壊死してしまっている状態で、残念ながら元には戻りません。
対策:症状が広がっている葉は、体力を消耗させるため、葉柄の付け根から清潔なハサミで切り取ります。そして、即座に10℃以上ある暖かい部屋へ避難させてください。
葉に切れ込みが入らない理由
「うちのモンステラ、全然葉っぱが割れない…」という声も多いと思います。
せっかくモンステラを育てるなら、あのカッコいい切れ込みが入ってほしいですよね。
これは病気や肥料不足ではなく、主な原因は2つです。
1. 光量不足(ほぼこれです)
これが最大の原因です。モンステラは、十分な光を浴びて大きく成長することで、「下の葉にも光が届くように」と葉が割れる(切れ込みが入る)ようになると言われています。
暗い場所ではその必要がないため、切れ込みのない幼葉(切れ込みのないハート型の葉)のまま成長してしまうんですね。
2. 株の成熟度
まだ株が若い(幼い)場合、十分な光を当てていても、切れ込みは入りません。
ある程度の大きさに成熟して(一般的に本葉が5〜6枚以上展開して)初めて、切れ込みのある葉を展開し始めます。
対策は、やはり「植物育成ライトを導入する」か、「より明るい日陰に置き場所を変更する」ことです。
しっかり光を与えて株を成熟させてあげることが、切れ込みへの一番の近道です。
茎がひょろひょろ伸びる(徒長)
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)
葉に切れ込みが入らないのと同様に、茎だけが間延びしてひょろひょろと伸びてしまう「徒長(とちょう)」も、典型的な「光量不足」のサインです。
少しでも多くの光を浴びようと、光の差す方向へ必死に茎を伸ばしている状態です。
葉と葉の間隔(節間)が長く、バランスが悪くなり、見た目も不格好になりがちです。
徒長の対策と仕立て直し
対策は、葉に切れ込みが入らない場合とまったく同じです。植物育成ライトで安定した光を補ってあげるか、置き場所そのものを見直す必要があります。
すでにひょろひょろに伸びてしまった部分は、残念ながら元には戻りません。
見た目を整えたい場合は、生育期(5月〜9月)に、元気な節(成長点や気根のすぐ上)で切り戻し(剪定)て、新しい芽が吹くのを待つ「仕立て直し」が必要になります。
切った茎は「挿し木」や「茎伏せ」で増やすこともできますよ。
ヒメモンステラも日陰は苦手?
よく「ヒメモンステラ」という名前で売られている、葉が小さくて切れ込みが可愛い植物がありますよね。
あの小ぶりな感じが玄関にもぴったり、と思うかもしれません。
実はあれ、モンステラ属(Monstera)ではなく「ラフィドフォラ属(Rhaphidophora)」の「ラフィドフォラ・テトラスペルマ」という別の植物なんです(豆知識です!)。
ですが、育てる上での性質はモンステラとそっくりです。
耐陰性がある植物として紹介されることも多いですが、やはり極端に暗い日陰は苦手で、光が足りないとモンステラ同様に間延びしたり葉色があせたりします。
結論として、ヒメモンステラも「モンステラと全く同じ管理が必要」と考えてOKです。
暗い玄関に置く場合は、同じように育成ライトが必須になりますね。
まとめ:モンステラの玄関の日陰管理
ここまでお疲れ様でした。モンステラを玄関の日陰で育てるのは、「『条件付きで可能』というのが私の結論です。
「日陰に強い」という言葉だけを信じて暗い玄関に置いてしまうと、高確率で失敗してしまいます。
でも、玄関という環境の「光・温度・風」のリスクをしっかり理解して、適切な対策を講じれば、元気に育てることも夢ではありません。
玄関で成功するための3つの鍵
- 環境の客観視:ご自宅の玄関の「暗さ」レベルを客観的に把握すること。(照度計アプリなども活用!)
- 光の追加(最重要):「暗い玄関」や「普通の玄関」なら、植物育成ライトを導入すること。これが最も確実な投資です。
- 光以外の管理の徹底:光が少ない分、「水やり(徹底的に乾燥を確認)」と「風通し(サーキュレーター)」に細心の注意を払うこと。
環境さえ整えてあげれば、モンステラは玄関の素敵なシンボルツリーになってくれるはずです。
ぜひ今回の内容を参考に、ご自宅の環境に合わせた管理方法を見つけてみてくださいね。
関連記事はこちら!
-



モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術
-



モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方
-



モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説
-



モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ
-



モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ
-



モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術
-



モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方
-



失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法
-



モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説
-



モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説
-



モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ
-



モンステラが倒れる原因と復活法!支柱や植え替えで解決するコツ
-



モンステラの風水で玄関の運気UP!方角別の効果と枯らさない育て方
-



モンステラが枯れる原因と復活法|葉の変色や症状別の対策を解説
-



モンステラに似た植物11選!葉が割れる種類や猫に安全な代用種も
-



伸びすぎたモンステラは植え替えで解決!失敗しない剪定と支柱のコツ
-



モンステラを地植えで庭に植えるには?失敗しない土作りと冬越しの鉄則
-



モンステラの葉が丸まるのはSOSサイン!症状の見分け方と復活法を解説
-



モンステラの新芽が出ない原因は?動かない理由と復活させる対処法
-



モンステラが大きくならない・成長しないサインを見極める根腐れチェックと復活法
-



モンステラの水耕栽培でメダカとの共生は可能?毒性と安全に栽培する方法を解説
-



暴れるモンステラをセリアの支柱で救出!失敗しない立て方と100均おしゃれ活用術
-



モンステラの葉焼け対処法|変色した葉の切り方・復活法と根腐れとの見分け方
-



モンステラ「ホワイトタイガー」はなぜ高い?組織培養できない希少性と適正相場