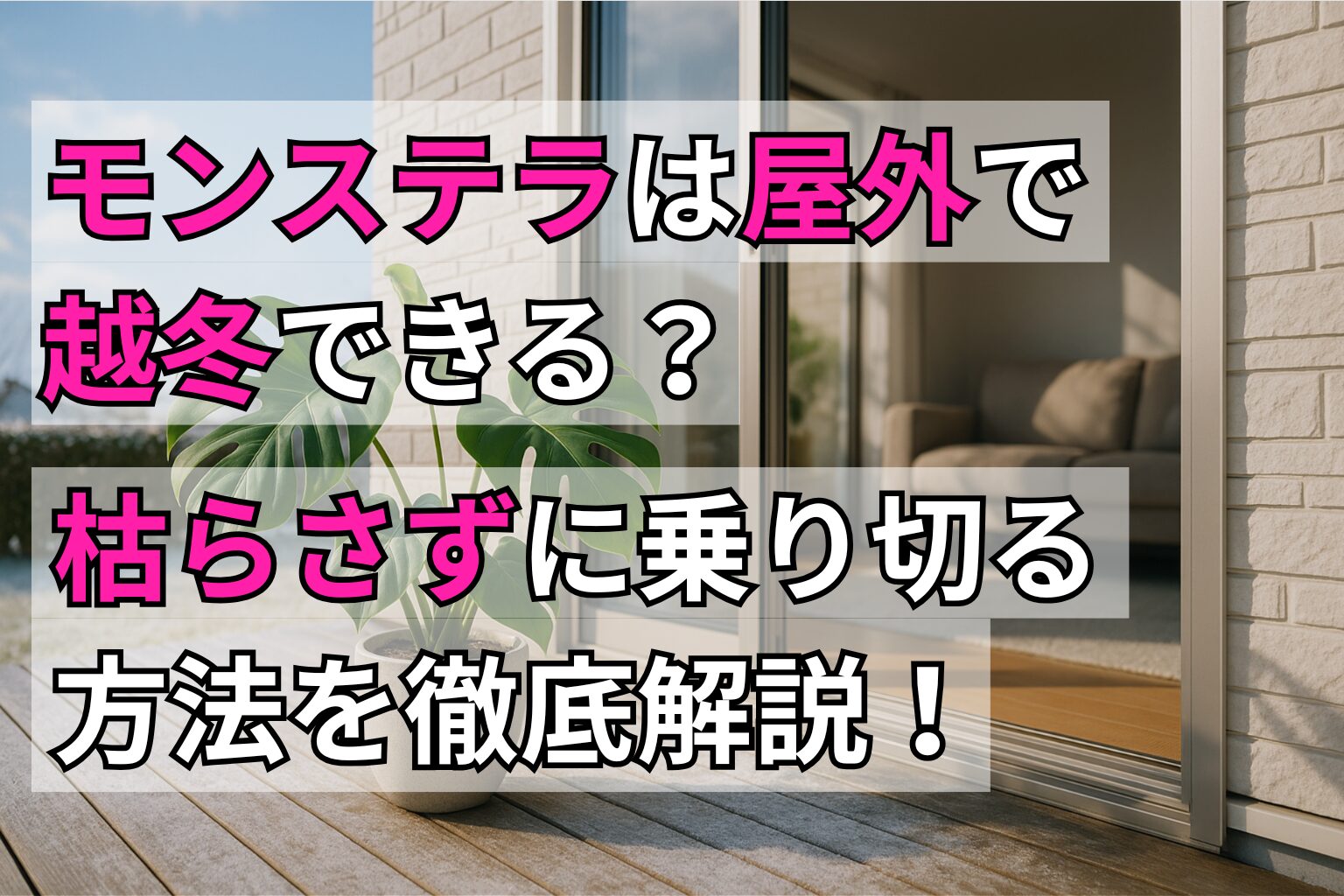観葉植物として絶大な人気を誇るモンステラ。そのユニークで美しい葉姿を、お部屋の中だけでなく、ベランダや庭といった屋外スペースでも楽しみたいと考える方は少なくないでしょう。
しかし、熱帯アメリカのジャングルを故郷とするモンステラにとって、日本の冬は過酷な試練の季節です。屋外での越冬には、不安や疑問がつきまといます。
「そもそもモンステラは外でも大丈夫なのか」「屋外で育てる場合の具体的な寒さ対策はどうすればいいのだろうか」といった基本的な疑問から、冬は一体何度まで耐えられるのか、そして具体的に冬はどこに置くべきなのか、最適な管理方法を知りたいですよね。
特に、生育期とは全く異なる冬の断水に近い水やり頻度や、冬は日光に当ててもいいのかといった細かな管理のポイントは、失敗や後悔を避け、大切な株を守るために不可欠な知識です。
万が一、屋外で寒さにやられたり、葉が枯れたりした場合の復活方法や、予期せず出てきた冬の新芽の扱い方まで、事前にしっかりと理解しておけば、安心して冬を迎えることができます。
この記事では、モンステラの屋外越冬に関するあらゆる疑問を一つひとつ丁寧に解消し、あなたのモンステラを元気に春まで導くための専門的な知識と具体的な実践方法を、網羅的に詳しく解説していきます。
- モンステラが屋外で冬を越せる具体的な気象条件と限界温度
- 失敗しないための冬の置き場所選びと水やり管理の鉄則
- 寒さで弱ってしまった場合の症状別・適切な復活アプローチ
- 地植えや鉢植えで効果を発揮する事前の具体的な寒さ対策
モンステラを屋外で越冬させる基本と事前準備

モンステラの屋外越冬を成功させるためには、まずその植物が持つ基本的な性質を理解し、日本の冬の環境に対応するための事前準備を怠らないことが不可欠です。
ここでは、越冬の可否から耐寒温度、最適な置き場所、そして具体的な寒さ対策まで、冬を迎える前に必ず押さえておくべき基本事項を掘り下げて解説します。
- モンステラは外でも大丈夫?外で育てる基本
- 冬は何度まで耐えられる?耐寒温度の目安
- 冬はどこに置くべき?最適な置き場所
- 事前に知りたいモンステラの寒さ対策
モンステラは外でも大丈夫?外で育てる基本

モンステラは、本来、年間を通して温暖で湿度の高い熱帯アメリカのジャングルに自生する植物です。他の高木に寄り添いながら光を求めて成長するたくましさを持っています。
そのため、日本の気候で言えば、温暖な春から秋にかけては、屋外の環境がむしろモンステラの成長を力強く促進させることが少なくありません。
屋外で育てることで、鉢の中だけでは得られない自然の風や変化のある光を感じ、より葉が大きく、茎も太い、野性味あふれる丈夫な株に育つ可能性があります。
しかし、その成長の恩恵を享受できるのは暖かい季節に限られます。
最大の問題となるのが、冬の厳しい寒さです。モンステラの耐寒性はそれほど高くなく、日本の冬、特に気温が氷点下に達するような厳しい寒さや、植物の細胞を直接破壊する霜、そして株全体を物理的・生理的に痛めつける雪は、モンステラにとって大きな脅威となります。
したがって、「モンステラは適切な条件下でのみ、屋外でも育てられる」というのが基本的な考え方です。一年を通じて屋外に放置できる植物ではなく、特に冬越しには細心の注意を払った場所選びと管理が絶対に必要となります。
鉢植えと地植えの基本的な考え方
- 鉢植えの場合:
移動が可能なため、季節や天候に応じて最適な場所へ移す「移動管理」が基本となります。これが最も安全で推奨される方法です。 - 地植えの場合:
移動ができないため、より一層の寒さ対策が必須です。また、そもそも冬越しが可能な温暖な地域であるかどうかの見極めが、成功の鍵を強く握ります。

冬は何度まで耐えられる?耐寒温度の目安

モンステラの屋外越冬計画を立てる上で、最も重要な科学的指標が「耐寒温度」です。
どのくらいの寒さまで耐えられるのか、その限界点を正確に把握しておくことが、成功と失敗を分ける決定的な要因となります。
一般的に、モンステラの耐寒温度は5℃が限界ラインとされています。これを下回る環境に長時間さらされると、葉が黒く変色し、細胞内の水分が凍結して組織が破壊され、枯死に至るリスクが非常に高まります。
ただ、あくまでこれは「耐えられる最低限の温度」であり、株にとっては大きなストレスがかかっている状態です。
より安全に、そして春からのスムーズな成長を促すためには、最低でも10℃以上をキープすることが理想的な温度です。
気温が10℃を下回ると、モンステラの成長は著しく鈍化し、生命活動を維持するための「休眠状態」に入ります。
このデリケートな状態で厳しい寒さに繰り返し直面すると、株全体の活力が徐々に奪われ、春になっても回復できないほどの深刻なダメージを負うことがあります。
また、温度計の数字だけでなく、以下の2つの気象条件はモンステラにとって致命的なダメージを与えるため、絶対に避けなければなりません。
- 霜(しも):
霜が葉に直接降りると、その部分の葉の組織が凍結し、黒く水浸状になって枯れてしまいます。一度霜にやられてしまった葉は、決して元には戻りません。屋根のある軒下など、霜が直接当たらない場所で管理することが、屋外越冬の最低絶対条件です。 - 雪:
雪が積もると、その物理的な重みで茎が簡単に折れてしまうだけでなく、極度の低温と過剰な湿気で株全体が深刻なダメージを受けます。降雪が常態的に見られる地域での屋外越冬は、専用のビニールハウスなどの特別な設備がない限り、極めて難しいと考えられます。
これらの点を総合すると、まずは住んでいる地域の冬の平均最低気温や過去の最低気温記録を事前に確認することが重要です。5℃を下回る日が多い場合や、霜が頻繁に降りる環境では、屋外での越冬は慎重に判断し、室内への退避を基本戦略とすべきです。
ちなみに、e-stat(政府統計の総合窓口)HPによると、2023年度調査における全国各地の最低気温※は沖縄県の14.9℃、鹿児島県の5.0℃を除き全て5℃を下回っているため、基本的に屋外での越冬は厳しい環境下におかれることが考えられます。
※日最低気温の月平均の最低値
冬はどこに置くべき?最適な置き場所

冬のモンステラの置き場所は、越冬の成否を9割方決定づけると言っても過言ではない、極めて重要な要素です。
厳しい寒さや冬特有の脅威から株を守りつつ、休眠期に必要な最低限の日光を確保できる戦略的な場所を選ぶ必要があります。
鉢植えの場合:機動力を最大限に活かす
鉢植えの最大のメリットは「移動できること」です。この利点を最大限に活かし、日中と夜間、天候に応じて場所を変える柔軟な管理を心がけましょう。
- 基本の場所(日中):
冷たい北風や霜、雪を確実に避けられる「軒下」や「屋根のあるベランダ・テラス」が最適です。特に、日中に柔らかい日差しが差し込む建物の南側や東側などが望ましいでしょう。壁際に置くことで、建物からの放射熱による保温効果もわずかながら期待できます。 - 夜間や特に冷え込む日の避難場所:
天気予報で最低気温が5℃を下回る予報の日や、風が強く吹く日は、夜間だけでも無暖房の玄関や廊下、物置などの室内に取り込むことで、格段に安全性が高まります。この際、急激な温度変化は株にストレスを与えるため、暖房の効いた暖かいリビングなどに直接入れるのではなく、まずは涼しい場所で寒さに慣らすのが賢明なポイントです。
地植えの場合:植え付け場所がすべて
地植えは移動ができないため、植え付けの段階で冬の過酷な環境を十分に想定しておくことが絶対条件となります。
- 理想的な植え付け場所:
建物の南側で、冬の冷たい北風を完全に遮ることができる壁際などが最も適しています。周囲に他の常緑樹や塀などの構造物があることで、夜間の放射冷却が和らぎ、霜が降りにくくなる「マイクロクライメート(微気候)」が形成されるため、生存確率が上がります。 - 注意点と地域の見極め:
関東以南の比較的温暖な沿岸部(湘南エリアなど)や、都市部のヒートアイランド現象の影響を受ける場所では、地植えでの越冬事例も報告されています。しかし、これらは気候的に恵まれた例外的なケースと捉えるべきです。冬に土壌が凍結するような寒冷地や内陸部での地植え越冬は、ほぼ不可能と考えられます。また、越冬可能な地域であっても、株がまだ若くて小さい場合や、その年の冬が特に厳しい「厳冬(げんとう)」の場合は、後述する徹底した寒さ対策が必須となります。
事前に知りたいモンステラの寒さ対策

モンステラを屋外で冬越しさせるためには、最適な置き場所を選ぶ工夫に加えて、より積極的な寒さ対策を施すことで成功率を大きく向上させることができます。本格的な冬が到来する12月より前の、気温が下がり始める11月頃から準備を始めるのが理想的です。
具体的な寒さ対策
| 対策方法 | 対象 | 期待できる効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| マルチング | 鉢植え・地植え | 根の保温、地温の安定、土の凍結防止 | 蒸れの原因になることもあるため、素材の選択が重要 |
| 不織布/ビニール | 鉢植え・地植え | 防風、防霜、保温(外気より1〜2℃上昇) | 日中は外し、蒸れを防ぐ。ビニールは要空気穴 |
| 二重鉢 | 鉢植え | 根鉢の保温、断熱効果 | 鉢のサイズと重量が増す |
| 簡易ビニールハウス | 鉢植え | 高い防寒・防霜・防雪効果 | 日中の温度管理(換気)が必須 |
鉢植え・地植え共通の対策
- マルチング:
株元の土の表面を、バークチップや腐葉土、ヤシがら、わらなどで5cmほどの厚さに覆う方法です。これにより、地面からの冷気が直接根に伝わるのを防ぎ、地温の急激な低下を和らげることができます。根を寒さから守るための最も基本的で効果的な対策の一つです。 - 不織布やビニールで覆う:
夜間や特に冷え込む日に、株全体を不織布(寒冷紗)や大きなビニール袋で覆います。これにより、冷たい風が直接葉に当たるのを防ぎ、霜が降りるのを物理的に遮断します。また、植物自身の呼吸熱や地面からの放射熱が内部にこもり、外気より1~2℃高く保つ保温効果も期待できます。日中は日光を当てるため、また内部の湿度が上がりすぎて蒸れるのを防ぐために、必ず外すことを忘れないようにしましょう。ビニールを使用する場合は、数カ所に空気穴を開けておくと通気性が確保できます。
鉢植え向けの対策
- 二重鉢(鉢カバー):
育てている鉢よりも一回りから二回り大きな鉢やおしゃれな鉢カバーに入れ、その隙間にバークチップ、新聞紙、発泡スチロールの破片などを詰め込みます。これにより、鉢の周りに空気の層ができ、優れた断熱効果が生まれて根を寒さから効果的に守ります。 - 簡易ビニールハウス:
ベランダや庭先に設置できる家庭用の小型ビニール温室を利用するのも非常に効果的な方法です。霜や雪、寒風を完全にシャットアウトできるため、より安全に冬越しさせることが可能です。ただし、晴れた日の日中は内部の温度が急上昇し、植物を傷める可能性があるため、ファスナーを開けるなどして換気を忘れずに行う必要があります。
これらの対策は、一つだけを行うよりも複数を組み合わせることで、より高い防寒効果を発揮します。
お住まいの環境やその年の冬の厳しさに合わせて、最適な対策を講じることが、モンステラを無事に春へと導くための賢明な判断となります。
モンステラを屋外で越冬させる管理術・コツ

基本と事前準備が整ったら、次はいよいよ冬本番の管理術です。冬のモンステラは「休眠期」に入るため、成長期と同じ感覚で手入れを続けると、かえって株を弱らせる致命的な原因になりかねません。
ここでは、水やりや日照、肥料といった日々の管理のコツから、万が一のトラブルへの対処法まで、具体的なテクニックを詳しく解説します。
- 冬の断水は必要?水やり頻度の見極め方
- 冬は日光に当ててもいい?日照管理のコツ
- 冬の肥料は与えるべき?
- 外で寒さにやられた・枯れた時の復活方法
- モンステラの冬の新芽はどうすればいい?
| 管理項目 | 冬の管理ポイント | 特に注意すべき点 |
|---|---|---|
| 水やり | 頻度を大幅に減らし、徹底的に乾燥気味に管理。土が完全に乾いてから数日後に与える程度。 | 根腐れの最大の原因。水のやりすぎは厳禁。受け皿の水は必ず即座に捨てる。 |
| 日当たり | 柔らかい日光に当てる。日照不足による徒長に注意しつつ、窓際の夜間の冷気に気をつける。 | 夏の強烈な直射日光とは異なり、冬の貴重な日差しは体力の維持に必要。 |
| 肥料 | 原則として一切与えない(完全な休眠期)。 | 肥料焼けを起こし、休んでいる根を深刻に傷める原因になる。 |
| 置き場所 | 霜や雪、寒風を避けられる軒下などが基本。5℃以下になる予報の日は室内へ退避させる。 | 特に夜間の急激な冷え込みに最も注意が必要。天気予報のチェックを習慣に。 |
冬の断水は必要?水やり頻度の見極め方

冬のモンステラ管理で最も多くの人が失敗し、株を枯らしてしまう原因が「水やり」です。
気温が10℃を下回ると、モンステラは自らの生命活動を最小限に抑える「休眠期」に入ります。
この時期は光合成の量も減り、成長も止まるため、水の吸収量が劇的に減少します。
この状態で成長期と同じ感覚で水を与え続けると、土が常に湿った状態になり、根が酸素不足に陥って呼吸できずに腐ってしまう、最も恐ろしい「根腐れ」を引き起こします。
「冬は断水する」という言葉を耳にすることもありますが、これは文字通り完全に水やりを止めるという意味ではありません。
正しくは「断水に近いほど、水やりの頻度を大幅に減らし、土を徹底的に乾かす期間を設ける」と理解するのが極めて重要です。
水やりの具体的な頻度とタイミング
- 頻度の目安:
お住まいの環境や鉢の大きさにもよりますが、「土の表面が乾いてから、さらに数日から1週間程度待ってから」というのが一つの目安です。結果的に、月に2~3回程度の水やりになることも珍しくありません。 - 見極めるためのテクニック:
- 指で確認:
土の表面だけでなく、鉢の中に指を第2関節(2~3cm)まで入れてみて、中の土まで完全に乾いているかを必ず確認します。表面が乾いていても、中はまだ湿っていることがよくあります。 - 鉢の重さで確認:
鉢を持ち上げてみて、水やり後のずっしりとした重さと比べて、明らかに軽くなっているかを確認します。これは非常に有効な方法です。
- 指で確認:
- 与える量と時間帯:
水やりをすると決めたら、暖かい日の午前中に行い、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与えます。これにより、土の中の古い空気を押し出し、新しい空気を根に供給する効果もあります。冷たい水道水は根に刺激を与えるため、室温にしばらく置いた常温の水を使うのが理想的です。そして、受け皿に溜まった水は、根腐れの直接的な原因となるため、必ずすぐに捨ててください。
冬の水やりは「与えなさすぎで枯れるのではないか」と心配するよりも、「与えすぎによる根腐れをいかに防ぐか」を最優先に考えることが、越冬を成功させる最大のコツです。
冬は日光に当ててもいい?日照管理のコツ

冬のモンステラにとって、日光は休眠期であっても生命活動を維持するための貴重なエネルギー源です。しかし、夏の管理とは異なる注意点があり、当て方には少し工夫が必要です。
休眠期とはいえ、わずかながらも光合成を行うことで株の体力を維持し、春からの成長再開に備えるため、日照管理は重要なポイントとなります。
冬の日光の当て方
- 基本は「柔らかい光」を長時間:
夏の強烈な直射日光が「葉焼け」の原因になるのとは対照的に、冬の日差しは比較的弱いため、積極的に当ててあげましょう。遮光ネットなどは不要で、レースカーテン越しのような、柔らかい光が長時間当たる場所が理想的です。 - 日照不足のリスク:
冬は日照時間が短くなるため、日当たりが悪い場所に置きっぱなしにすると、光を求めて茎がひょろひょろと間延びしてしまう「徒長(とちょう)」の原因になります。徒長した株は見た目が悪いだけでなく、細胞壁が薄くなり病原菌に侵されやすくなるため、病気にもかかりやすくなります。
屋外管理での注意点
屋外で管理している場合、日当たりの良い場所は、同時に夜間の放射冷却によって最も冷え込みやすい場所でもあるというジレンマがあります。
日中は日当たりの良い軒下で管理し、夕方以降は冷気を避けられる壁際に移動させるか、不織布で覆うなどの対策が必要です。
特に注意したいのが、室内から屋外へ出す際の急激な環境変化です。
例えば、暖かい室内で管理していた株を、天気が良いからといって急に冷たい屋外へ出して日光浴させると、温度差のショックで株が弱ることがあります。
日光浴させる場合も、まずは短時間から始め、徐々に屋外の環境に慣らしていくように慎重に行いましょう。
冬の肥料は与えるべき?

冬のモンステラに肥料を与えるべきかという疑問に対する答えは、非常に明確でシンプルです。「原則として、冬の期間(おおよそ11月~3月頃)は、肥料を一切与えないでください」。これが鉄則です。
冬に肥料が不要かつ有害な理由
- 休眠期のため栄養を吸収できない
前述の通り、冬のモンステラは成長活動をほぼ停止させる休眠状態に入っています。人間で言えば、深い眠りについているようなものです。この時期に肥料という「食事」を与えても、根が栄養を吸収することができません。 - 「肥料焼け」という深刻なリスク
吸収されずに土の中に残った肥料成分は、土壌内の塩類濃度を異常に高めてしまいます。これにより、浸透圧のバランスが崩れ、根が水分を吸収するどころか、逆に水分を奪われてしまう「肥料焼け」という深刻な現象を引き起こします。これは根を直接傷つけ、根腐れや株全体の致命的な衰弱に繋がります。
肥料を再開する最適なタイミング
肥料は、長い冬が終わり、春になって気温が安定して上昇し、モンステラが休眠から目覚めて成長を再開する兆候(新しい芽が明らかに動き出す、葉の展開が始まるなど)が見られてから与え始めます。具体的には、4月下旬から5月頃が適切なタイミングです。
活動を再開したばかりの根はまだデリケートなため、最初は規定よりも薄めた液体肥料から与え始めるなど、徐々に慣らしていくと株への負担が少なく、スムーズに成長期へと移行できます。
また、秋の終わりに与えた置き肥(固形肥料)がまだ土の表面に残っている場合は、冬に入る前に忘れずに取り除いておくと、意図しない肥料焼けを防ぐことができ、より安全です。
外で寒さにやられた・枯れた時の復活方法

十分な対策を講じていても、予期せぬ急な冷え込みや管理ミスによって、モンステラが寒さのダメージを受けてしまうことがあります。
葉が黒く変色したり、茎が力なく垂れ下がったりする姿を見ると、もうダメかもしれないと諦めてしまいがちです。
しかし、すぐに見捨てる必要はありません。茎や根の中心部が生きている限り、復活の可能性は十分にあります。冷静に、そして迅速に対処することが重要です。
症状別の対処手順
まずは一刻も早く、これ以上のダメージを防ぐために、霜や寒風の当たらない、最低でも5℃以上を保てる場所(無暖房の室内や玄関など)へ避難させます。
注意点として、急に暖房の効いた20℃以上の暖かい部屋に入れると、急激な温度変化がさらなるストレスとなるため、まずは涼しい場所で徐々に環境に慣らさせましょう。
- 葉が黒く変色・水浸状になった場合:
その部分は寒さで細胞が完全に壊死している状態です。残念ながら元に戻ることはなく、放置するとカビや病気の温床になるため、清潔なハサミで、葉柄(葉の付け根の茎)の根元から切り取ります。 - 茎がぶよぶよと柔らかくなった場合:
茎の内部まで凍結し、腐敗が始まっている可能性があります。この場合も放置は危険です。腐敗部分を指で軽く押し、硬くて健康な部分まで切り戻します。切り口がきれいな緑色であれば、そこから復活する可能性があります。
- 水やりは徹底して控える:
ダメージを受けた株は、水の吸収力が著しく低下しています。この状態で水を与えると、確実に根腐れを起こします。土が完全にカラカラに乾くまで水やりは控え、徹底して乾燥気味に管理します。葉の乾燥が気になる場合は、霧吹きで軽く葉水を与える程度に留めましょう。 - 春まで静かに見守る:
外科的処置と水分管理を徹底した状態で、暖かい場所で静かに春の訪れを待ちます。茎や根に生命力が残っていれば、気温が上昇してくると、節々から新しい芽が出てくる可能性があります。この復活プロセスには数ヶ月かかることもあるため、焦らずに見守る忍耐力が大切です。
モンステラの冬の新芽はどうすればいい?

冬の期間中でも、室内管理などで15℃以上の比較的暖かい環境が保たれていると、モンステラが休眠せずに活動を続け、新しい芽を出すことがあります。
これは株が元気である証拠であり、喜ばしいサインではありますが、冬に出てきた新芽は非常にデリケートなため、少し特別な注意が必要です。
冬の新芽を守るための管理ポイント
- 絶対的な寒さからの保護:
新芽は成葉に比べて細胞壁が薄く、寒さに対する抵抗力が全くありません。一度でも5℃以下の冷気に当たると、簡単に黒く傷んでしまい、成長が止まってしまいます。新芽が出ている株は、特に夜間の温度管理に細心の注意を払い、窓際など冷え込みやすい場所から必ず離して管理しましょう。 - 無理に成長を促さない(厳禁):
新芽が出てきたからといって、「もっと大きくしたい」という親心から肥料を与えたり、水やりの頻度を増やしたりするのは絶対に禁物です。前述の通り、冬は株全体としては本来休眠期であり、根の活動は鈍っています。ここで余計な水分や栄養を与えると、根腐れや肥料焼けを引き起こし、株全体を危険に晒すことになります。冬の管理の基本(乾燥気味の水やり、無肥料)は、新芽が出ていても必ず維持してください。 - 自然のペースに任せる:
基本的には、そのまま静かに見守るのが最善の策です。無理に日当たりの良い場所に移動させたりせず、現在の置き場所で安定した環境を保ち続けることが大切です。その新芽は、ゆっくりとしたペースで展開するかもしれませんが、本格的な成長は春になってからと割り切りましょう。
冬の新芽は、あなたが適切な冬越し管理ができているという証拠です。
過保護になりすぎず、基本的な冬の管理を淡々と徹底することが、その新芽を無事に美しい葉へと育てるための最も確実な鍵となります。
まとめ:モンステラを屋外で越冬させるための成功ポイント
この記事で解説してきた、モンステラを屋外で越冬させるための重要なポイントを、最後に総まとめとして以下にリストアップします。
これらの要点を確実に押さえることが、あなたの愛するモンステラを厳しい冬から守り抜き、元気に春を迎えさせてあげるための成功の鍵となります。
- モンステラの屋外越冬は不可能ではなく、適切な条件下で可能
- 耐寒温度の絶対的な限界ラインは5℃、安全圏は10℃以上を維持
- 植物の細胞を破壊する霜と雪は絶対に避けなければならない
- 基本的な置き場所は霜と冷たい北風を避けられる軒下や屋根のある場所
- 夜間や気温が5℃以下になる日は室内へ取り込むのが最も安全な方法
- 地植えでの越冬は温暖な地域以外では非常に高いリスクを伴う
- 株元のマルチングや不織布での保護は有効な寒さ対策となる
- 冬の水やりは断水に近いほど頻度を劇的に減らし、徹底的に乾燥気味に管理する
- 水やりは土の中まで完全に乾いていることを指で確認してから行う
- 水やり後の受け皿に溜まった水は根腐れの元なので必ず捨てる
- 冬の弱く短い日差しは、株の体力維持のための貴重なエネルギー源となる
- 成長が止まる休眠期である冬の期間は、肥料を一切与えない
- 寒さで黒く傷んだ葉は元に戻らないため、病気予防のためにも剪定する
- 茎や根が生きていれば、ダメージを受けた株でも春に復活の可能性があるため諦めない
- 冬に出てきたデリケートな新芽は、特に寒さに当てないよう細心の注意を払って見守る
関連記事はこちら!
-

モンステラが大きくなりすぎ・成長しすぎた時の対処法!失敗しない剪定術
-



モンステラの土の配合はこれ!室内で虫がわかない黄金比率と作り方
-



モンステラタウエリーの特徴と育て方!デリシオーサとの違いや大きさを徹底解説
-



モンステラが折れた時の対処法!復活させる応急処置と再生のコツ
-



モンステラがダイソーで売ってない?入荷時期と在庫確認のコツ
-



モンステラの水耕栽培はずっとできる?根腐れを防ぐ管理と冬越し術
-



モンステラは赤玉土だけで育つ!室内で清潔に楽しむ土の選び方と育て方
-



失敗しないモンステラの寄せ植え!相性の良い植物と枯らさない管理法
-



モンステラの葉っぱが茶色くなる原因とは?切るべき判断基準と復活法を解説
-



モンステラの葉っぱから水が!葉から水滴が出る理由と床濡れ対策を解説
-



モンステラの剪定と水差し|失敗しない切る場所と発根管理のコツ