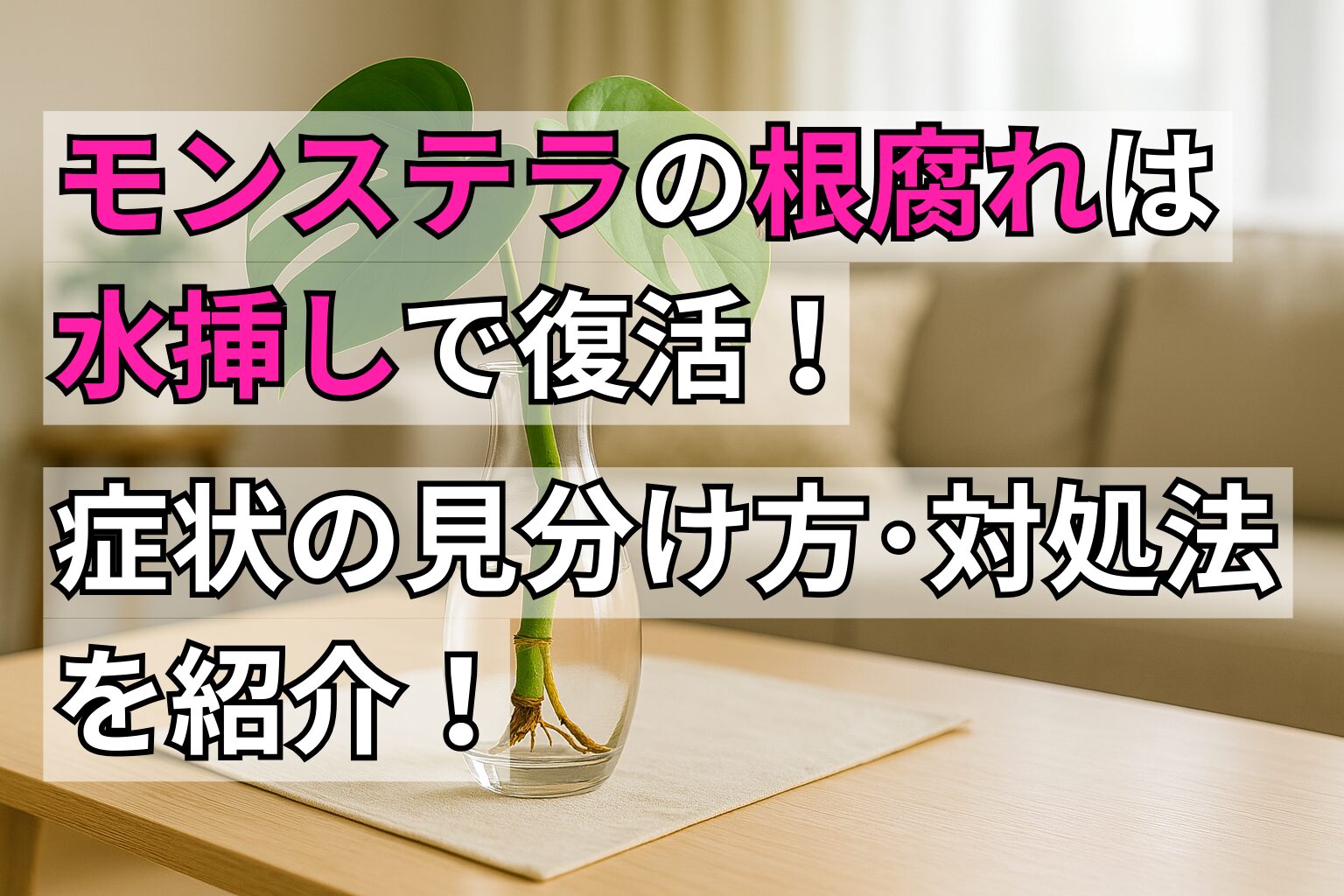モンステラの根腐れで悩まされているあなたは、水挿しによる改善の可能性について気になっているのではないでしょうか。また、根腐れの見分け方や応急処置、水差しでブヨブヨになったときの対策、茎だけの水差しで発根するのかといった、具体的な判断材料を探しているはず。
この記事では、根腐れの症状を実際の画像で紹介し、根腐れしたら最初に何をすべきか、腐った部分をどこまで切るか、メネデールの適切な使い方、植え替えが難しい冬の対応までを体系的に解説します。
適切な手順を踏めば復活は十分狙えるので、ぜひ最後まで御覧ください。
- 根腐れの見分け方と初期から末期までの症状
- 水挿しで起きるトラブルの原因と再発防止のコツ
- 根腐れ時の切る位置の判断とメネデールの活用ポイント
- 冬の植え替え方法や水挿しから土へ戻す手順
モンステラの根腐れは水挿しで解決!基本知識

- 根腐れの症状と対処方法
- 根腐れの症状を画像で確認
- モンステラに水をさすとどうなる?
- 水差しにしたら茎だけで発根するか
- 水差しでブヨブヨになる原因と対策
根腐れの症状と対処方法

根腐れとは、土壌中の酸素不足や病原性微生物(例:糸状菌や卵菌)によって根が機能不全に陥る現象で、進行段階によって兆候が変化します。
初期では乾湿サイクルが乱れ、鉢内が常に湿った状態になりがちです。中期になると土や鉢からの異臭、葉のしおれ、茎のしわなど、地上部にも異常が表れます。後期では茎の根元が黒ずみ軟化し、末期には株全体が自立できず倒れ込みます。
このように、早い段階で原因に手を打つことが、回復率と再発防止の両面で有利に働きます。
以下に症状と対処方法を整理しました。なお、室温は15〜25℃に保つと根の代謝が安定しやすいとされています。
| 進行段階 | 主なサイン | 対処方法 |
|---|---|---|
| 初期 | 土が乾かない 葉の張りが弱い 受け皿に常時水 | 水やりを止めて乾燥を促す 風通しと明るい日陰で管理 受け皿の水を廃棄 乾燥後に活力剤を水で薄めて使用 |
| 中期 | 腐敗臭・カビ臭 表土の藻・カビ コバエが湧く | 鉢から抜いて根を確認 腐敗根を除去し新しい清潔な用土に植え替える |
| 後期 | 茎元が黒くブヨブヨ。押すと潰れて戻らない | 健康な上部を確保し、節を含めて挿し木や水挿しに切り替え |
| 末期 | 株が倒れる 全体が軟化し、しおれる。 | 生きている節を探して挿し穂を確保 救済困難な場合は新たに栽培することも検討 |
初期〜中期は、竹串を鉢中心まで挿して引き抜き、湿り具合を触感で確かめる方法が有効です。表土だけで判断せず、鉢の中心部が乾いてから水を与えるサイクルへ戻すことが再発抑制の近道と言えます。
室内ではサーキュレーターで緩やかな気流をつくると、表土の乾燥と土中の酸素供給を助けます。
根の切除は清潔な刃物で行い、切断面を滑らかに整えると感染リスクを下げられます。
なお、根の健全・不健全の典型所見(健全=丈夫でしなやか、腐敗=どろどろして茶色くなり、脆く臭いがする)は、アメリカのサウスダコタ州立大学HPでも情報が発信されています。
根腐れの症状を画像で確認

まず前提として、根腐れの症状はモンステラの各部位(根、茎基部、葉、土・鉢)によって異なります。自分が育てているモンステラが根腐れしているかどうかは、各部位を目視などでチェックすることで把握できます。
| 部位 | 健全な状態 | 要注意のサイン |
|---|---|---|
| 根 | 白〜クリーム色 弾力あり 表皮が密着 | 褐変〜黒化 ぬめり 表皮が剥離し芯だけ残る |
| 茎基部 | 硬く締まり、押すと戻る | 黒ずみ・半透明化・軟化 押すと凹んだまま 茶色くなる |
| 葉 | ハリ・ツヤがある 濃い緑色 葉脈は明瞭 | 全体的に黄色い 葉柄にしわがある 先端から透明化 |
| 土・鉢 | 水やり後に適度に乾く 臭いがない | 常に湿っている 藻・カビが生えている 腐敗臭がする 受け皿に水が溜まっている |
実際に根腐れになってしまったモンステラを育てている事例を、画像でご紹介します。
それぞれ根が黒変・ブヨブヨになってしまったり、葉に元気がないのがわかります。
モンステラに水をさすとどうなる?

水挿しは、傷んだ根をいったん切り離して清潔な水環境で新根を出させる再生プロセスとして有効です。
透明な容器を使えば、発根点(節)から伸びる白い新根や水の濁りを目視管理でき、早期の異常検知にもつながります。
一方で、長く水挿しを続けると水中に特化した細く柔らかい根(通気性の乏しい環境に適応した根)が増え、土壌へ戻した際に環境のギャップで一時的なしおれや活着不良が起こりやすくなります。
これを避けるには、発根後に段階的に環境を切り替える前提で短期運用するのが安全です。
水挿し運用のコツ
- 温度・光:
室温15〜25℃、直射日光を避けた明るい日陰で管理します。水温の急変は溶存酸素量の低下や菌の増殖に直結するため、窓辺の直射・暖房直風・冷気の当たりすぎは避けます。 - 水質:
2〜3日に一度の水替えと容器の洗浄を習慣化し、濁りや臭いがあれば即日交換します。刃物は消毒し、切り口は繊維を潰さず滑らかに整えます。 - 水位:
節が常に1〜2cm水没する程度に保ち、葉や上位の茎は水から出します。浸しすぎは酸欠と軟化の原因となります。
短期リハビリとしての使い分け
- 目的:
根腐れ後の回復や挿し穂の発根など、数週間〜数カ月の再生を想定 - 終了目安:
新根が3〜5cm、側根が出始めたら移行の準備段階 - 土への移行:
通気性の高い観葉植物用培養土に手早く植え付け、1〜2週間は半日陰で養生。最初の水やりはたっぷり与え、その後は乾湿リズムを整えます。肥料は活着後にごく薄めから
| 方法 | 主なメリット | 想定リスク | 管理の要点 |
|---|---|---|---|
| 短期の水挿し | 清潔・観察が容易・発根管理がしやすい | 長期化で水中に特化した細く柔らかい根が増える。 | 水替え頻度維持、早期に土へ段階移行 |
| 長期の水耕(インテリア) | 土を使わず清潔感、維持が簡便 | 大株化しにくい、栄養管理が限定的 | 根の剪定、水質維持材の活用、適度な補光 |
水差しにしたら茎だけで発根するか

水挿しをした場合、残念ながら茎だけで発根することはありません。
水挿しでの発根は、茎の節が担います。葉柄だけでは器官形成点(節)がないため根になりにくいため、節を含む茎を必ず確保してください。節が発根点になること、切り口を節直下(節間に沿って節から2.5~5cm下)で用意することについてはアメリカのミネソタ大学HPの記事でも取り上げられています
さらに、節に気根が付いている挿し穂は、既に根になる準備ができた部分があるため、根が出始めるまでの時間が短くなりやすいです。
水挿しを成功に導くためには、「気根が付いている節を含む茎」を挿し穂として選ぶことが重要。
なお、水挿しが成功しやすい環境要因を以下のとおりまとめました。
- 容器は透明だと根の色や清潔度を観察しやすく、細長い口の花瓶は挿し穂を垂直に保持しやすい。
- 水位は、節と切り口の位置が常に水に触れる高さに保ちつつ、葉や上位の茎を沈めない。
➡目安は、高さ3~4cmとし、節に付いている気根は水に浸かるようにする。 - 水温が低いと細胞分裂が鈍化し、逆に高温だと溶存酸素が低下して嫌気的になり腐敗が進む(発根の生理は温度・酸素・清潔度に左右される)。
- 室温は15〜25℃、直射日光を避けた明るい日陰をキープする。
- 容器は2〜3日に一度のペースで水替えと内壁のぬめり洗浄を行うと環境が安定する。
- 刃物は70%前後のアルコールで消毒し、切り口は繊維を潰さず滑らかに整えると感染が起こりにくくなる。
発根までの目安と環境
発根開始の目安は環境が整えば5~14日程度です。
白い新根が伸び始めたら、根が水中に十分触れるよう水位を微調整しつつ、にごりや臭いの有無をこまめに点検します。
根の評価は「色・張り・分枝」の3点で行い、白〜クリーム色であればハリがあり、側根が見え始めたら順調です。
3〜5cmに伸びると吸水が安定するため、以降は土へ移行するか水栽培を継続するかを選べます。
土へ移す場合は、根を乾かさないよう手早く、観葉植物用の通気性の高い培養土へ。最初の1〜2週間は直射を避け、用土が乾き切る前に軽めの水やりで慣らすと活着しやすくなります。
| 根の状態 | 推奨アクション | 管理の要点 |
|---|---|---|
| 発根前(0〜1cm未満) | 水挿し継続 | 15〜25℃、明るい日陰、水替え2〜3日に1回 |
| 1〜3cm | 水挿し継続または移行準備 | 清潔維持、切り口の黒変やぬめりの有無をチェック |
| 3〜5cm | 土へ移行または水栽培継続 | 土へ移行時は根を折らないよう植え付け、半日陰で養生 |
| 5cm以上+側根多数 | 土への移行適期 | 初回の水やりはたっぷり、その後は乾湿リズムを作っていく |
水差しでブヨブヨになる原因と対策

水挿し(水差し)中に茎がブヨブヨに軟化する原因は主に三つあります。
- 細菌・真菌・卵菌などの微生物が切り口や傷から侵入し、組織が水びたし様に崩れる。
- 水位が高すぎて本来空気に触れるべき部位まで長時間水没し、酸素欠乏で細胞が壊れる。
- 直射日光で水温が急上昇または冬季の低温で代謝が落ち、腐敗が進む。
➡いずれも、衛生・水位・温度の3つの管理で多くは回避可能。
切り戻しは早めが肝心です。軟化部を越えて健全な組織まで戻し、清潔なはさみで繊維を潰さない角度でスパッと切ります。切断面を水で軽く洗い流し、必要に応じて数分、自然乾燥させてから水に挿すと良いでしょう。
水位は「根だけを浸し、茎や葉は出す」を厳守し、直射は避けてカーテン越しの明るさを確保します。水は2〜3日に一度交換し、容器のぬめりはスポンジで優しく除去します。
再発が続く場合は、ゼオライトや珪酸塩白土などの根腐れ防止剤を底に少量敷くと水質が緩やかに安定します。
具体的なチェック内容と復旧のステップ
- 観察:
色(黒変・半透明化)、触感(押して戻るか)、臭い(腐敗臭)を確認。 - 切除:
軟化が止む位置まで戻し、節を1つ以上残すように再カット。 - 消毒:
刃物はアルコールで消毒、容器も中性洗剤で洗浄しよくすすぐ。 - 再セット:
節が1〜2cm水没、水温は常温、明るい日陰で静置。 - 日々のメンテナンス:
水替えは2〜3日に1回、にごり・ぬめり・臭いがあれば即日交換。 - 温度管理:
冬は15℃以上、夏は直射で水温が上がらない位置に移動。
以上の基本を徹底すると、茎の硬さが戻り、生長点が再び活動しやすくなります。
軟化部が広範囲に及ぶ場合でも、健全な節を確保できれば挿し穂としての再起は十分見込めます。
モンステラが根腐れした時の水挿しの具体的な方法
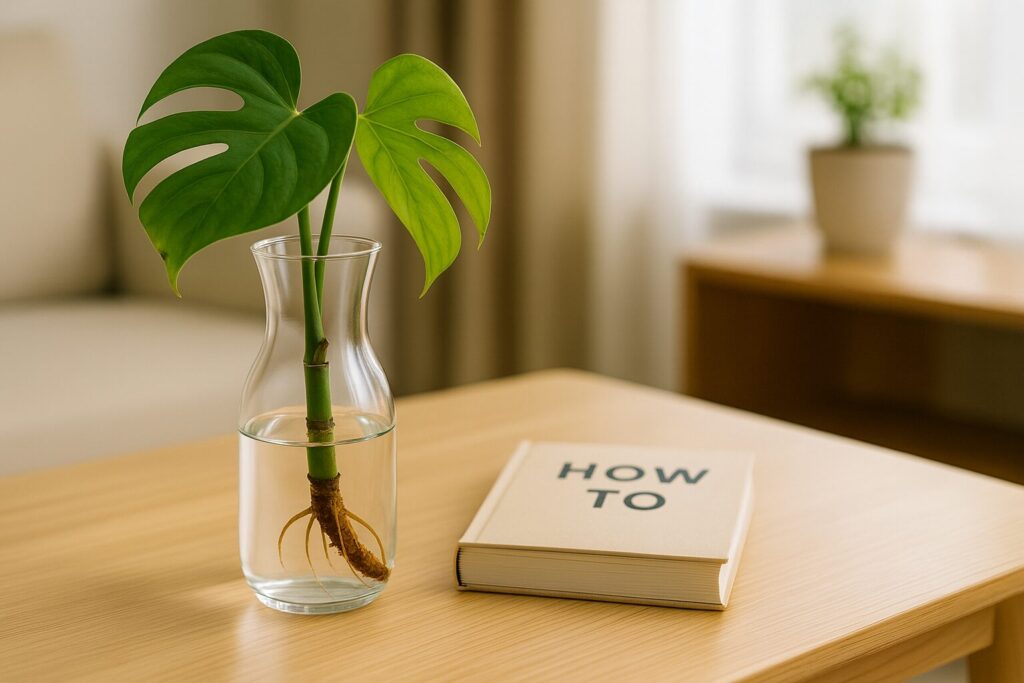
- 根腐れしたらまず何をするか
- 腐った根や茎を切る判断基準
- メネデールの使い方と注意点
- 冬に根腐れしても植え替えはできる!注意点を解説
- まとめ:モンステラの根腐れは水挿しで対処しよう!
根腐れしたらまず何をするか

根腐れした時に最優先すべきは、モンステラの根圏の状態を観察し、根腐れの原因となっている「湿りすぎ」を改善することです。
一度水やりを中止し、風通しの良い明るい日陰へ移動させます。
受け皿の水は必ず捨て、鉢の外側が冷たく湿っている場合は蒸散による負荷を下げるため直射日光や高温を避けます。
初日:観察・初期対応(切除など)
鉢からの異臭、土表面の白カビ、コバエの増加などがあれば根腐れ進行のサインです。
可能なら鉢から株を抜き、根色(健全:白〜クリーム/不良:黒・褐色でぬめり)、根皮の脱落(芯だけ残る)を確認します。
腐った根はハサミで切除し、健全な白根と節を残します。刃物はアルコール消毒し、切断面は水で軽くすすいでから風に当てて短時間乾かします。
初日~3日目:再セットと環境の安定化
状態に応じて以下対応を試みます。
- 軽症(初期):
新しい通気性の良い培養土へ植え替え、鉢サイズは現状より大きくしすぎないように調整します。肥料は活着まで控えます。 - 中等度〜重症:
節を含む健全な茎を選び、水挿しで再生ルートへ。透明で清潔な容器にセットし、水位は節が1〜2cm水没、室温は15〜20℃を目安に保ちます。 - 共通管理:
2〜3日に一度の水替え・容器洗浄をルーティン化し、直射日光と過度な低温を避けます。サーキュレーターで緩やかに空気を動かすと乾湿リズムが整います。
1〜2週間:状態安定までの見守り
- 葉:
新たな黄変が広がらないか、葉先の丸まりやしわの進行がないかを確認します。 - 茎基部:
押して形が戻る硬さが維持されているか、黒変や水浸様の拡大がないかを観察します。 - 根:
水挿しでは白い新根の伸長、鉢管理では土の乾き具合と軽さを手で確かめ、水やりは「鉢中心まで乾いてから」を徹底します。
| 症状 | 優先事項 | 注意点 |
|---|---|---|
| 土が乾かない・軽いしおれ | 水やり停止、風通し改善 | 受け皿の水を捨て、直射回避 |
| 異臭・カビ・コバエ | 株の抜き取り診断、腐った根の除去 | 刃物・手指・容器の消毒をし、菌の侵入を防ぐ |
| 茎元の黒変・軟化 | 健全部位で切り戻し、水挿しへ | 節を残す、過水没を避ける |
| 株倒れ・広範な軟化 | 生きた節の救出と挿し穂化 | 失敗を想定し複数の節を確保 |
初動で共通するのは、過湿を断ち、衛生・温度・光・風の環境を整えることです。
これらを押さえるだけでも進行は大きく抑えられ、回復ルートに乗せやすくなります。
腐った根や茎を切る判断基準

切除の判断は、色・硬さ・臭いの三点を同時に確認すると精度が上がります。
- 色:
健全な根は白〜クリームで半透明感があり、先端がやや艶のある白色です。しかし、腐敗が進むと褐色〜黒色に変わり、表皮(外層)が靴下のようにズルリと脱皮状に剥がれて芯だけ残ります。茎は内部断面が白〜淡緑でみずみずしい層に達するまで健全、褐変や灰褐色の半透明層が続く場合はさらに上流側へ切り上げます。このとき、断面確認は一度で決めず、数mmずつ段階的に切り上げることを意識しましょう。 - 硬さ:
軽くつまんで弾力が保たれているかで見極めます。健全根は押し戻す弾性があり、腐った根は指圧で潰れます。茎基部は「押して形が戻る」かが目安で、ブヨブヨして戻らない部分は切除対象です。 - 臭い:
腐敗臭(生ゴミのような匂い)や発酵臭が目安になります。無臭〜わずかな青臭さなら生きていますが、鼻を近づけると明確な異臭がある部位は、色・硬さの所見と合わせて除去を検討します。
再生の起点となる節・芽点・気根はできるだけ温存しましょう。節を一つ以上含めることで、発根・発芽の確率が上がるためです。
根量が大幅に減った場合は、葉の枚数を適度に整理して蒸散とのバランスを取ると回復が安定します。
なお、わずかな褐変のみで弾力と無臭が保たれる根は経過観察し、根量を減らしすぎない配慮も必要です。
メネデールの使い方と注意点

メネデールとは、植物へ与える栄養剤(サプリメント)のようなものです。植物の生長に欠かせない鉄を、根から吸収されやすいイオンの形で含む植物活力剤であり、発根を促し、元気な株に育てます(メネデール公式より)。
水挿しや植え替え直後は特に根・茎の成長が肝となるため、肥料とともに併せて使うことで成長を促進できます。
一般的な使用は約100倍希釈(例:水500mlに対して約5ml)で、水替えのたびに同濃度を維持して供給します。
切り口が新しい直後は、まず清水で24時間ほど様子を見るか、200倍前後の低濃度から始め、白い新根が見え始めた段階で100倍へ移行すると刺激が少なく運用しやすくなります。
(参考)希釈と計量の目安
| 作る量 | 200倍(穏やかに開始) | 100倍(標準) |
|---|---|---|
| 300ml | 1.5ml | 3ml |
| 500ml | 2.5ml | 5ml |
| 1L | 5ml | 10ml |
| 2L | 10ml | 20ml |
希釈液を作るときは園芸用の計量カップを使用します。園芸用のカップが無ければ、家庭用でも構いません。
なお、希釈は都度作成し、混合液の作り置きは避けてください。鉄イオンは空気中で酸化しやすく、時間経過で狙いの状態が変わる可能性があるためです。
- 水挿し時:
水替え(2〜3日に一度)ごとに希釈液で満たし、濁りや臭いが出たら日程前倒しで交換します。 - 土栽培への移行時:
初回の水やりを清水で行い、次回から100〜200倍を1〜2回併用して根の立ち上がりを促します。
また注意点として、他の活力剤との併用は沈殿や変質の原因になる可能性があるため、基本は単独で希釈・使用してください。
管理については直射日光・高温を避け、キャップを確実に閉めて保管し、子どもの手の届かない場所に置きましょう。
冬に根腐れしても植え替えはできる!注意点を解説

低温期は呼吸と根の分裂活動が鈍るため、冬の植え替えは原則として見送るのが無難です。ただし、やむを得ず実施する場合は、モンステラへのダメージを最小限に抑えることを意識しましょう。
まず作業環境を整えます。室温15〜20℃の明るい日陰を確保し、冷気が滞留する窓辺・玄関・エアコンの直風は避けます。
根洗いは手が感じて冷たくない程度のぬるま湯(おおむね25〜30℃)で行い、黒変・軟化・異臭のある根を取り除きます。
根量が大きく減った場合は、蒸散の負荷を下げるために葉を数枚へ整理し、鉢も一回り小さくして土量を抑えると過湿リスクを下げられます。
観葉植物用の配合土に軽石やパーライトを足して通気を高めると、低温期でも乾湿が回りやすくなります
冬は「水挿しで養生」も有力な選択肢
根腐れダメージが大きい株は、冬期の土挿しリスクを避けて水挿しで安全に養生し、春の気温上昇後に土へ戻す方法が現実的です。
水挿し中は2〜3日に一度の水替えと容器洗浄で清潔を保ち、根が3〜5cm程度に伸びて吸水が安定してから段階的に土へ移行します。
移行時は半日陰・やや湿り気の維持から始め、1〜2週間かけて乾湿のメリハリに慣らすとショックが小さくなります。
まとめ:モンステラの根腐れは水挿しで対処しよう!
- 初期の土が乾かない兆候を合図に水やり停止と環境点検を同時に進める。
- 中期の異臭や葉のしおれが出たら抜き取り診断と腐敗根の除去を行う。
- 後期の茎元の黒ずみと軟化は健全部で切り上げ挿し木や水挿しに切り替える。
- 受け皿の水は都度捨て明るい日陰と緩やかな送風で乾湿リズムを整える。
- 水挿しは節と気根を含む茎を用い清潔な透明容器で管理・観察する。
- 水位は節が常に少し浸かる高さに保ち葉や上位の茎は水から出しておく。
- 室温は15~25℃を維持し直射と急激な水温変化を避けて管理する。
- 水は2~3日に一度交換し容器のぬめりや濁りは早めに洗い流す。
- 茎がブヨブヨする場合は軟化部を越えて再カットし清潔な環境で再セットする。
- 切除の判断は色・硬さ・臭いを合わせて行い節や芽点は可能な限り残す。
- メネデールは低濃度から開始し標準希釈へ移行して使い過ぎを避ける。
- 冬の植え替えは原則見送り、やむを得ず実施する場合は水挿しで養生し温暖期に土へ戻す。
- 新根が3~5cm伸びたら通気性の良い土へ段階的に移行する。
- 土へ戻した直後は半日陰で管理し乾きすぎと過湿を避けて活着を促す。
- 日照・風通し・水やり・鉢サイズ・用土を定期点検し再発防止の運用を続ける。